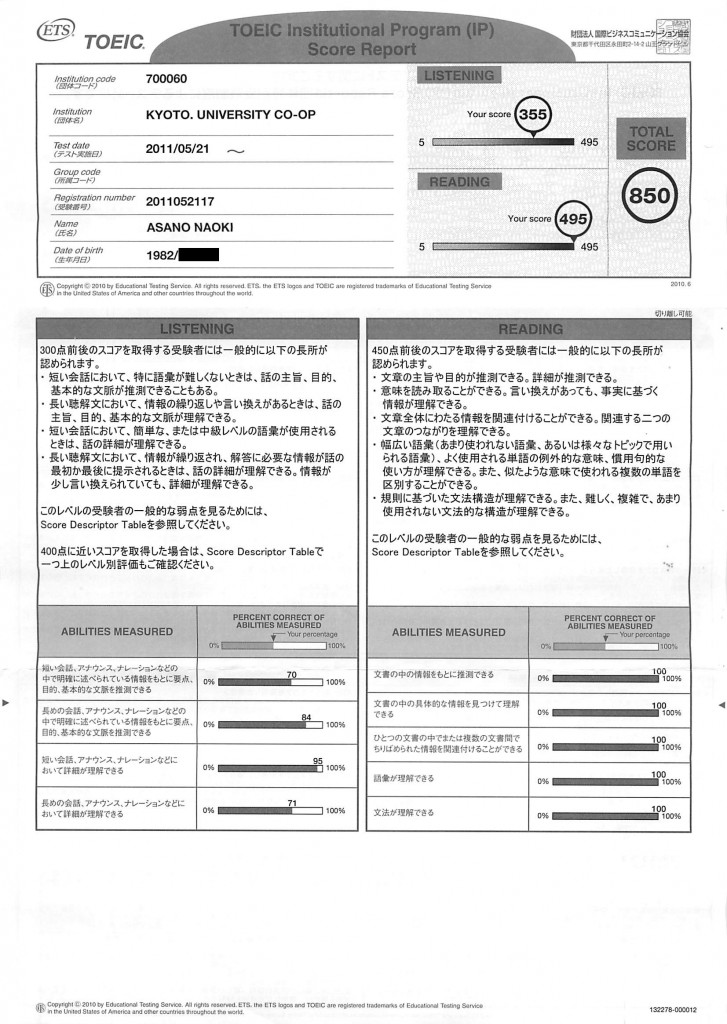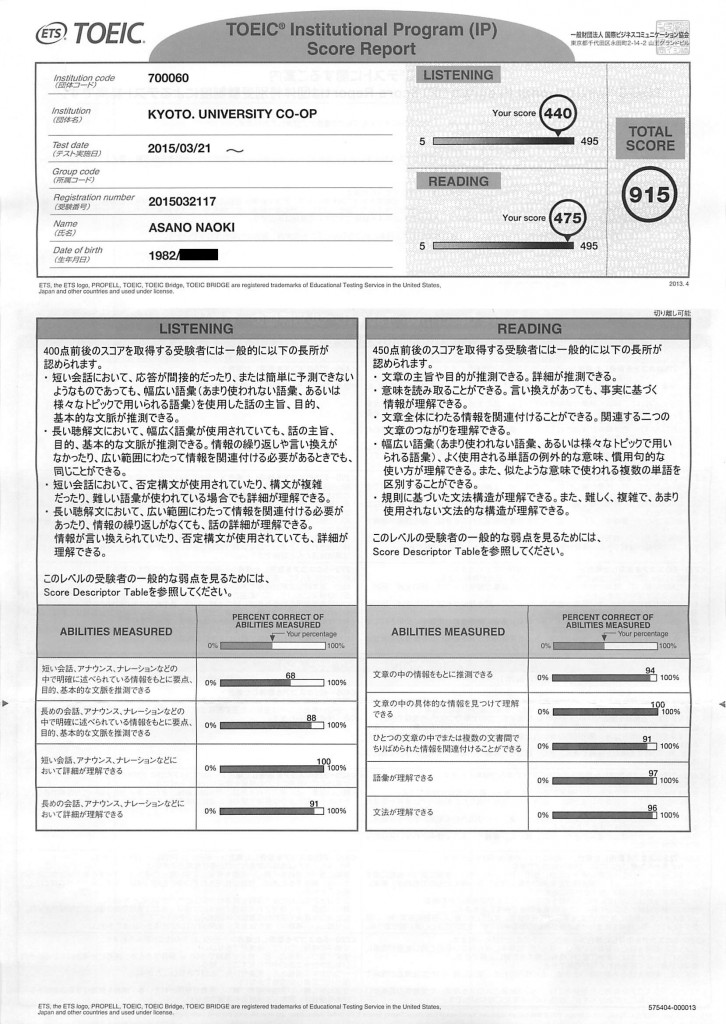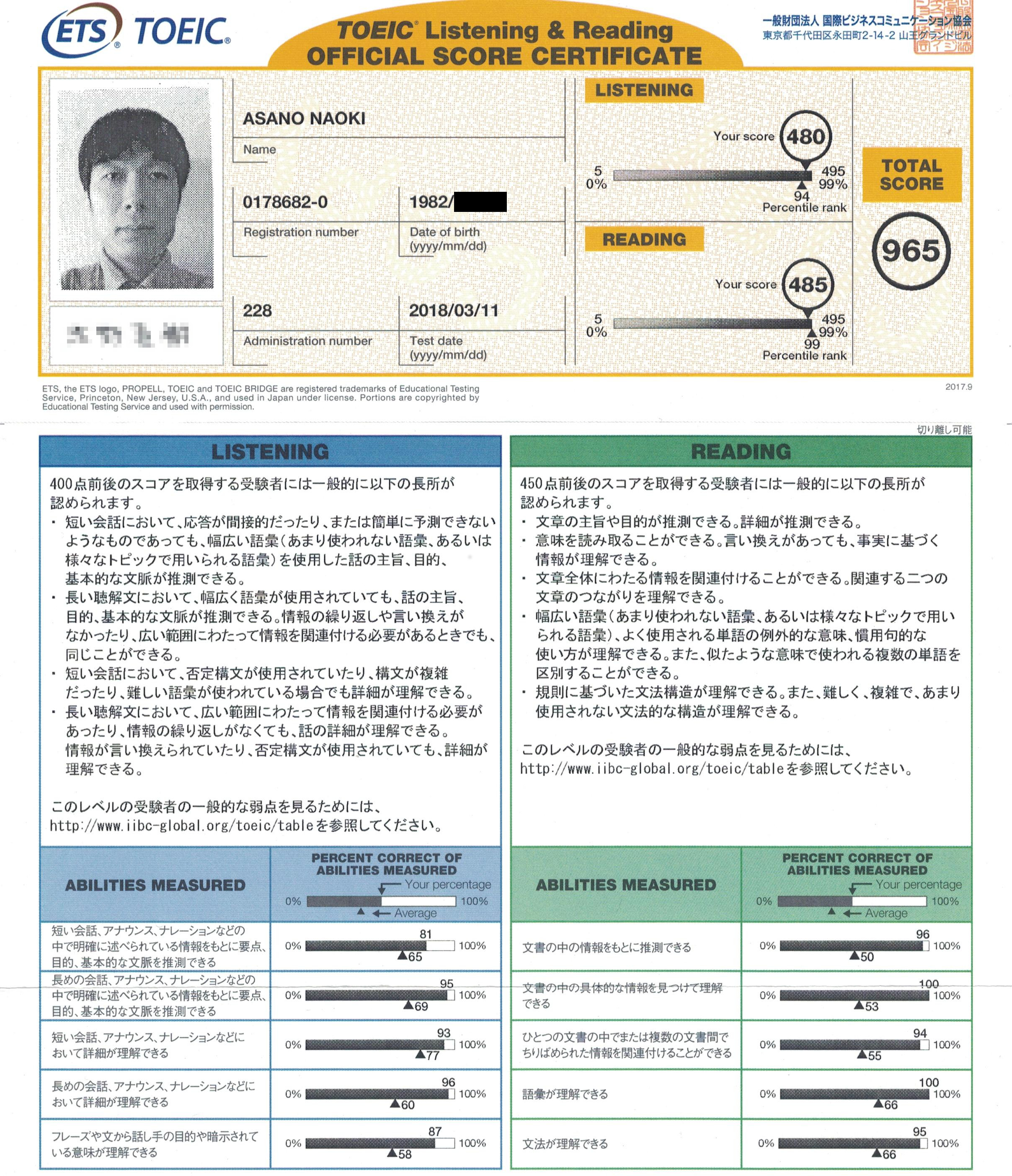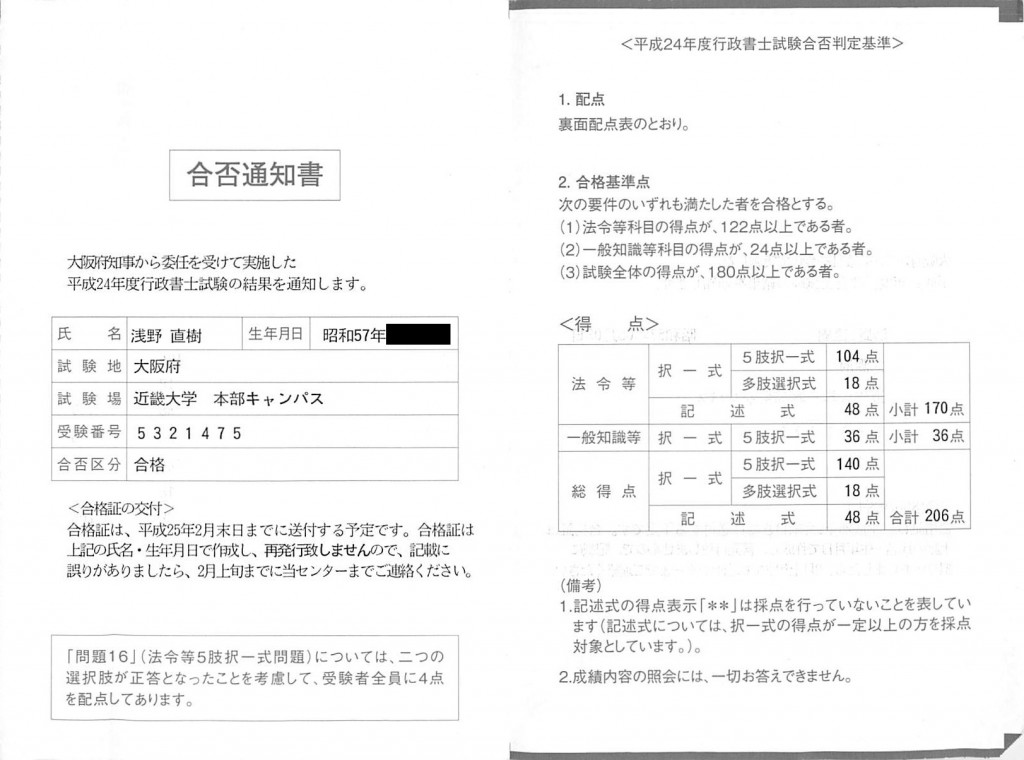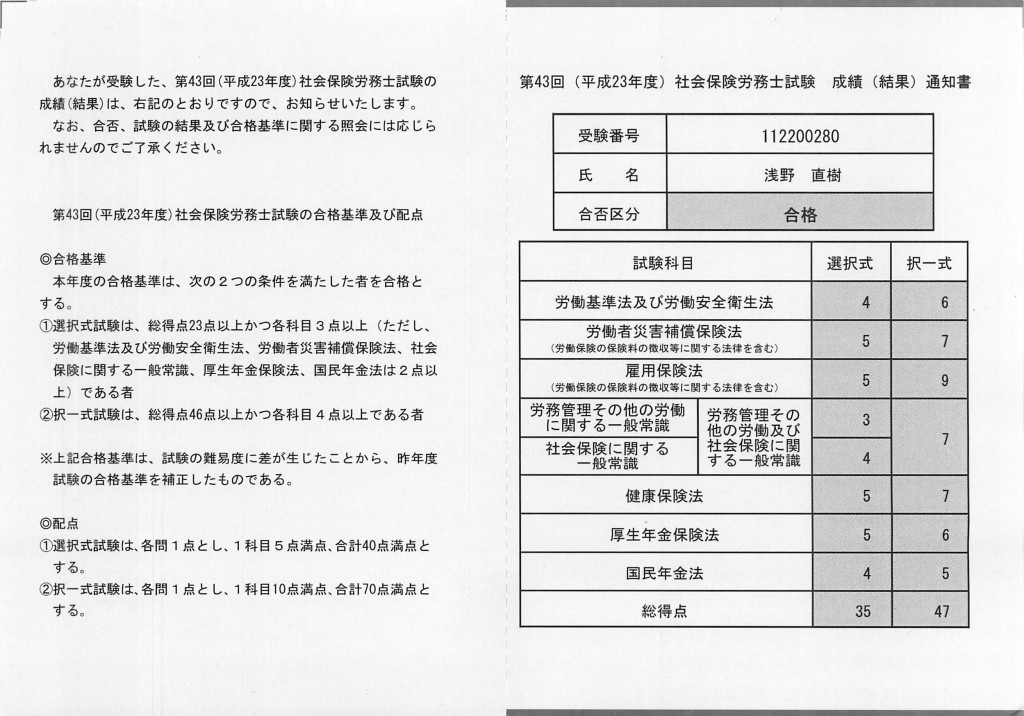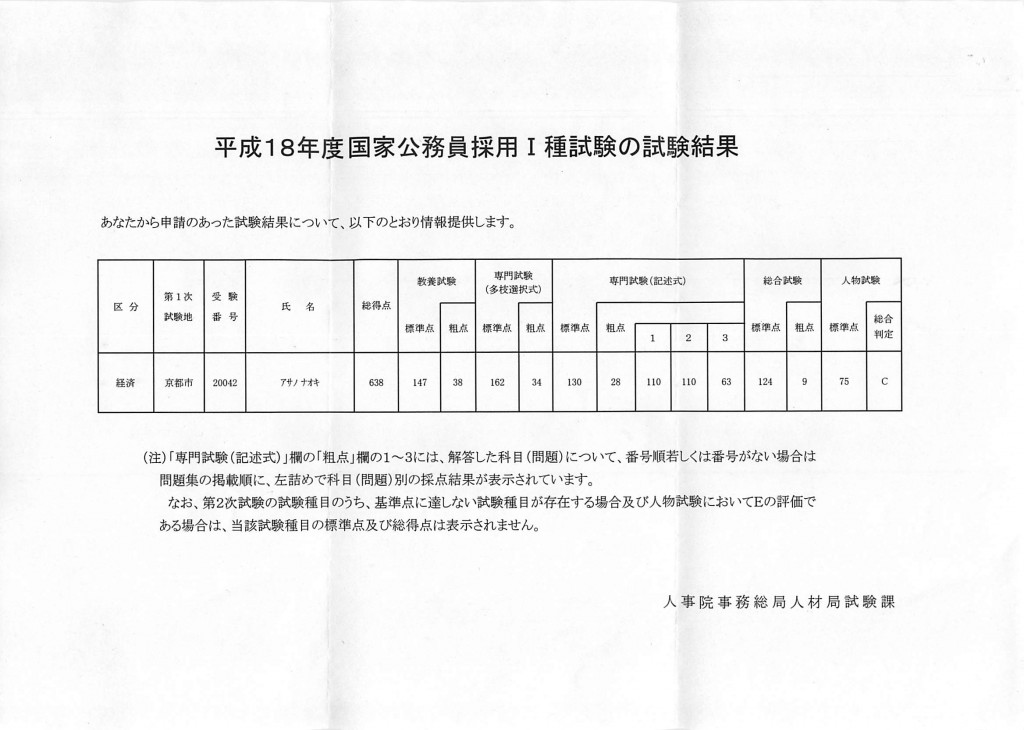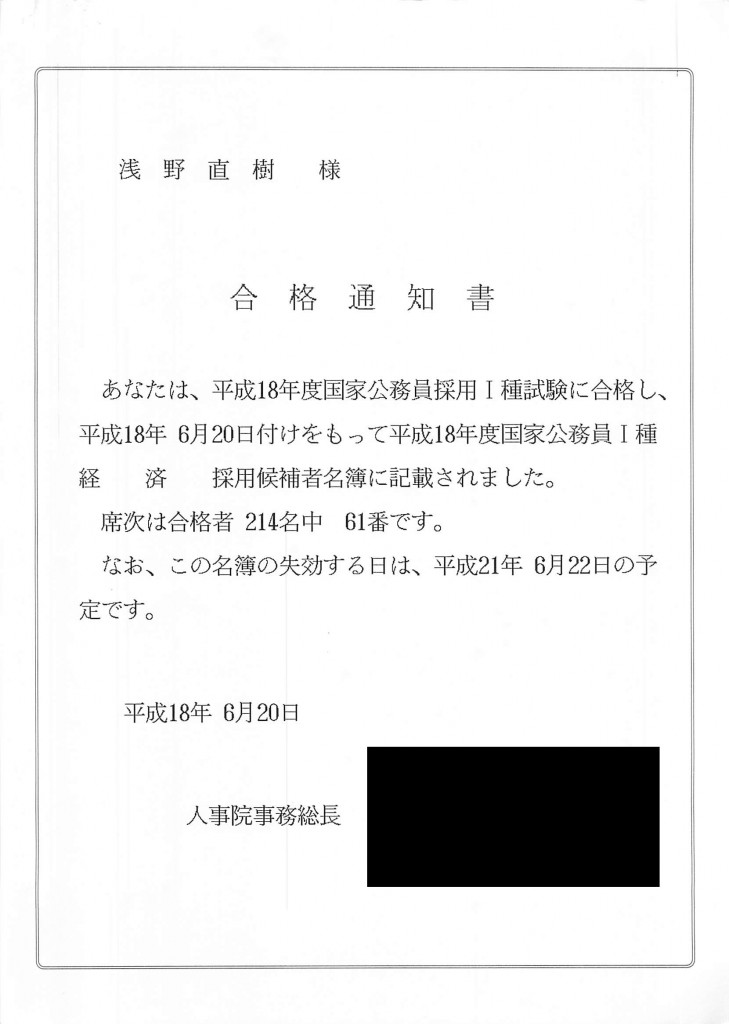主に自分用のメモとして、高校数学の教科書(解説)や問題を見ることができるサイトのリンク集を作りました。
教科書(解説)系
無料教科書の草分けでしょうか。昔はPDFファイルをダウンロードできたので、今でも探せばどこかにあるかもしれません。
上で紹介したFTEXTの発展形で現在も更新され続けています。質が高いです。
こちらも老舗のサイトです。わからないことを検索したときに見たことがある人も多いのではないでしょうか。
・高校数学の基本書(デジタル教科書:PDF) – さくらの個別指導(さくら教育研究所)
シンプルに要点を押さえた教科書です。
動画がメインですが、スライドのようなPDFを見ることもできます。
・受験の月
塾や予備校のように入試問題を実践的に解くための解説をしてもらいたいならここです。
・大学数学へのかけ橋!『高校数学+α:基礎と論理の物語』トップページ
その名前の通り「+α」の読み物です。余力があればどうぞ。
問題系
昔からあるサイトでありながら、最新の課程にも対応しています。中学数学もあります。
・数学目次
基礎基本を繰り返し行うドリル形式の問題集です。
各分野の標準的な問題があります。
作者が入試問題を解いてアップされているようです。
補充プリントや面白小問集があります。
・有名問題
チャート式や教科書傍用問題集にあるような有名問題のセレクションです。
数学の頭を使う問題から雑学的な話までたくさんあります。
大学別の過去問ならここが一番見やすいでしょう。
分野別の大学入試過去問ならここですね。
最後になりましたが、このような素晴らしいサイトの製作者のみなさまに感謝の意を表したいです。