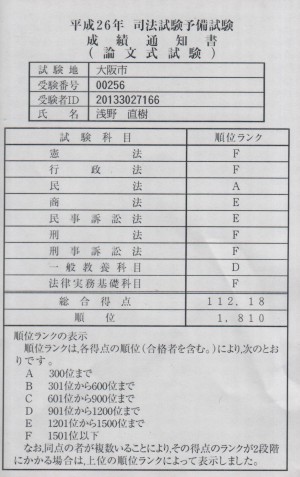問題
〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕,〔設問2〕及び〔設問3〕の配点の割合は,3:4:3〕)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
Ⅰ
【事実】
1.Aは,店舗を建設して料亭を開業するのに適した土地を探していたところ,平成2年(1990年)8月頃,希望する条件に沿う甲土地を見つけた。
甲土地は,その当時,Bが管理していたが,登記上は,Bの祖父Cが所有権登記名義人となっている。Cは,妻に先立たれた後,昭和60年(1985年)4月に死亡した。Cには子としてD及びEがいたが,Dは,昭和63年(1988年)7月に死亡した。Dの妻は,Dより先に死亡しており,また,Bは,Dの唯一の子である。
2.Aが,平成2年(1990年)9月頃,Bに対し甲土地を購入したい旨を申し入れたところ,Bは,その1か月後,Aに対し,甲土地を売却してもよいとする意向を伝えるとともに,「甲土地は,登記上は祖父Cの名義になっているが,Cが死亡した後,その相続について話合いをすることもなくDが管理してきた。Dが死亡してからは,自分が管理をしている。」と説明した。Aが,「Bを所有権登記名義人とする登記にすることはできないのか。」とBに尋ねたところ,Bは,「しばらく待ってほしい。」と答えた。
3.AとBは,平成2年(1990年)11月15日,甲土地を代金3600万円でBがAに売却することで合意した。そして,その日のうちに,Aは,Bに代金の全額を支払った。また,同月20日,Aは,甲土地を柵で囲み,その中央に「料亭「和南」建設予定地」という看板を立てた。
4.平成3年(1991年)11月頃,Aは,甲土地上に飲食店舗と自宅を兼ねる乙建物を建設し,同年12月10日,Aを所有権登記名義人とする乙建物の所有権の保存の登記がされた。そして,Aは,平成4年(1992年)3月14日から,乙建物で料亭「和南」の営業を開始した。なお,料亭「和南」の経営は,Aが個人の事業者としてするものである。
5.Aは,平成15年(2003年)2月1日に死亡した。Aの妻は既に死亡しており,FがAの唯一の子であった。Fは,他の料亭で修業をしていたところ,Aが死亡したため,料亭「和南」の営業を引き継いだ。乙建物は,Fが居住するようになり,また,同年4月21日,相続を原因としてAからFへの所有権の移転の登記がされた。
〔設問1〕 【事実】1から5までを前提として,以下の(1)及び(2)に答えなさい。
(1)⑴ Fは,Aが甲土地をBとの売買契約により取得したことに依拠して,Eに対し,甲土地の所有権が自己にあることを主張したい。この主張が認められるかどうかを検討しなさい。
(2)⑵ Fが,Eに対し,甲土地の占有が20年間継続したことを理由に,同土地の所有権を時効により取得したと主張するとき,【事実】3の下線を付した事実は,この取得時効の要件を論ずる上で法律上の意義を有するか,また,法律上の意義を有すると考えられるときに,どのような法律上の意義を有するか,理由を付して解答しなさい。
Ⅱ 【事実】1から5までに加え,以下の【事実】6から17までの経緯があった。
【事実】
6.料亭「和南」は順調に発展し,名店として評判となった。そこで,Fは,「和南」ブランドで,瓶詰の「和風だし」及びレトルト食品の「山菜おこわ」を販売することを考えるようになった。
7.まず,Fは,「和風だし」を2000箱分のみ製造し,二つの地域で試験的に販売することとした。そして,料亭「和南」とその周辺でF自らが1000箱分を販売するが,別の地域における販売は,食料品販売業者のGに任せることとし,FがGに「和風だし」1000箱を販売し,Gがそれを転売することとした。
8.「和風だし」は,一部に特殊な原材料が必要なことから,平成23年9月に製造する必要があった。しかし,試験販売の開始は,準備の都合上,平成24年3月からとされた。そこで,Fは,「和風だし」2000箱分を製造した上,販売開始時期まで,どこかに保管することを考えた。そして,甲土地のすぐ近くで,かつて質店を経営していたが,現在は廃業しているHならば,広い倉庫を所有しているだろうと考え,Hと交渉した結果,H所有の丙建物に,Fが製造した「和風だし」を出荷まで保管してもらい,これに対しFが保管料を支払うこととなった。
9.Fは,平成23年9月10日,Gとの間で,「和風だし」2000箱のうち1000箱をFがGに対し代金500万円で売却し,丙建物で同月25日にFがGに現実に引き渡す旨の契約を締結した。そして,平成23年9月25日,「和風だし」2000箱が丙建物に運び込まれ,そのうち1000箱がFからGに現実に引き渡された後直ちに,FとH,GとHは,それぞれ【別紙】の内容の寄託契約を締結した。これらの結果,丙建物では,合わせて「和風だし」2000箱が保管されることとなった。
なお,平成23年9月25日までに実際に製造された「和風だし」は予定どおり2000箱分であり,それ以外には,「和風だし」は製造されていない。また,製造された「和風だし」2000箱分は,種類及び品質が同一であり,包装も均一であった。
10.また,Fは,平成24年1月中には,料亭「和南」で飲食した顧客のために,お土産用「山菜おこわ」の販売を始めることとし,製造する「山菜おこわ」の保管場所につきHに相談した。Hは,既に「和風だし」の寄託を受けて丙建物が有効活用されていること,さらに,丙建物にはなお保管場所に余裕があることから,Fの「山菜おこわ」を丙建物において無償で保管することをFと合意した。
11.Fは,平成24年1月に入ると,「山菜おこわ」の製造を開始し,同月10日,Hの立会いを得て,「山菜おこわ」500箱を丙建物に運び込んだ。
12.平成24年1月12日,Fは,これまで取引のなかった大手百貨店Qの本部から,「山菜おこわ」をQ百貨店本店の地下1階食品売場で販売し,その評判が良ければ,「山菜おこわ」をQ百貨店の全店舗の食品売場で販売したいとの申出を受けた。
13.Fは,平成24年1月16日,Qとの間で,丙建物に保管されている「山菜おこわ」500箱をFがQに対し代金300万円で売却し,これを同月31日に丙建物で引き渡す旨の契約を締結した。Fは,この売買契約が成立したことから,Qが「山菜おこわ」の販売を始めるまでは,これを料亭「和南」で販売しないこととした。
14.Fは,Q百貨店で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえることになったことを大いに喜び,平成24年1月22日,たまたまHが料亭「和南」を訪れた際,「Q百貨店本店の食品売場に「山菜おこわ」を置いてもらえることになった。その評判が良ければ,Q百貨店は,全店舗で「山菜おこわ」を取り扱うことを申し出てくれている。「和南」の味を広める大きなチャンスだから張り切っている。」とHに話した。
15.ところが,平成24年1月24日,丙建物に何者かが侵入し,丙建物内に保管されていた「和風だし」2000箱のうち1000箱及び「山菜おこわ」500箱全てが盗取された。なお,丙建物に何者かが侵入することを許したのは,その日はHが丙建物の施錠を忘れていたためである。また,Fが,同月31日までに「山菜おこわ」500箱分を新たに製造することは不可能である。
16.Qにおいて,この盗難事件を受け,Fとの取引を進めるかどうかについて社内で協議したところ,Fの商品保管態勢が十分であるとはいえないとして,その経営姿勢に疑問が呈せられた。そこで,Qは,平成24年2月1日,「山菜おこわ」500箱分の売買契約を解除すること及び「山菜おこわ」販売に関するFQ間の交渉を打ち切ることをFに通知した。
17.なお,【事実】16までに記載した以外には,丙建物に保管されている「和風だし」及び「山菜おこわ」について出し入れはなく,丙建物に侵入した者は不明であり盗品を取り戻すことは不可能である。
また,「和風だし」及び「山菜おこわ」を丙建物で保管する行為は商行為ではなく,Hは商人でない。
〔設問2〕 Gは,Hに対し,丙建物に存在する「和風だし」1000箱を自己に引き渡すよう求めている。これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,その半分がもはや存在しないことと,残りの1000箱全てをGに引き渡せば,Fの権利を侵害することとを理由に,Gの請求に応ずることを拒んでいる。このHの主張に留意しながら,Gのする「和風だし」1000箱の引渡請求の全部又は一部が認められるか否かを検討しなさい。
〔設問3〕 Fは,Hに対し,「山菜おこわ」を目的とする寄託契約の債務不履行を理由として損害賠償を請求しようと考えている。この債務不履行の成否について検討した上で,Fが,【事実】16の下線を付した経過があったためQ百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなったことについての損害の賠償を請求することができるか否かについて論じなさい。
【別紙】
寄託契約書
第1条
寄託者は,受寄者に対し,料亭「和南」製「和風だし」1000箱(以下「本寄託物」という。)を寄託し,受寄者は,これを受領した。
第2条
1 受寄者は,本寄託物を丙建物において保管する。
2 受寄者は,本寄託物を善良な管理者の注意をもって保管する。
第3条
1 受寄者が他の者(次項及び次条において「他の寄託者」という。)との寄託契約に基づいて本寄託物と種類及び品質が同一である物を保管する場合において,受寄者は,その物と本寄託物とを区別することなく混合して保管すること(以下「混合保管」という。)ができ,寄託者は,これをあらかじめ承諾する。
2 前項の場合において,受寄者は,寄託者に対し,他の寄託者においても寄託物の混合保管がされることを承諾していることを保証する。
第4条
寄託者及び受寄者は,寄託者及び他の寄託者が,混合保管をされた物について,それぞれ寄託した物の数量の割合に応じ,寄託物の共有持分権を有することを確認する。
第5条
受寄者は,本寄託物に係る保管料を別に定める方法で計算し,寄託者に請求する。
第6条
受寄者は,寄託者に対し,混合保管をされていた物の中から,寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還する。
〔以下の条項は,省略。〕
練習答案
以下民法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
(1)
この主張は認められない。その理由を以下で説明する。
1985年4月の時点ではCが実体上も登記上も甲土地を所有していた。その時点でCが死亡することにより、Cの子であるDとEが法定相続分(第900条第4号)に従い、甲土地の持分を2分の1ずつ有することとなる(第882条)。これと異なる遺言や遺産分割の存在は確認できない。そしてその2分の1の甲土地の持分権を1988年7月にBが相続により*1取得した。
その後の1990年11月にBが甲土地をAに売るという売買契約が成立した。Aは契約成立日に代金を全額払っている。この時点でBは甲土地の持分を2分の1だけ有しており、残りの2分の1はEが有している。他人物売買も有効でありBは甲土地全部の所有権をAに移転する義務を負う(第560条)が、Eの協力がなければそれは不可能である。そして本件でEの協力があった形跡はない。よってAは甲土地の2分の1の持分は売買契約により取得するが、残りの2分の1の持分については取得しない。相続によりこのAの立場は包括的に承継したFは、甲土地の所有権について、2分の1の持分の限度について主張できるにすぎず、全部の所有権が自己にあるとの主張は認められない。
(2)
下線を付した事実は、この取得時効の要件を論ずる上で法律上の意義を有する。この取得時効は第162条第1項に規定されており、そこでは「所有の意思をもって」という要件が挙げられている。下線を付した事実は、この所有の意思を推認させるという法律上の意義を有する。
[設問2]
Gのする「和風だし」1000箱の引渡請求の全部が認められるが、Hは供託をすることによりその引渡義務を免れることができる。
FとH、GとHは、それぞれ別紙の内容の寄託契約を締結した。寄託契約書第1条によるとGはHに「和風だし」1000箱を寄託しており、同第6条により受寄者(H)は、寄託者(G)に対し、寄託者の寄託に係るものと同一数量のもの(「和風だし」1000箱)を返還する義務を負う。よってGのする「和風だし」1000箱の引渡請求の全部が認められることになる。
しかしHはFとも同様の寄託契約を結んでおり、Fの権利を侵害することを理由に、Gの請求に応ずることを拒んでいる。「和風だし」2000箱分は、種類及び品質が同一であり、包装も均一であったし、それらについてFとGは共有持分権を有する(寄託契約書第4条)ので、残存している1000箱がすべてGの寄託したものであるとは言えない。これは弁済者(H)が過失なく債権者を確知することができないときに当たるので、Hは供託をすることにより、その債務を免れることができる(第494条)。ここでの過失は債権者を確知することができないことに係る過失であり、「和風だし」1000箱が盗取されたことに係る過失ではないので、Hには過失がないと言える。
以上により冒頭で述べた結論となる。
[設問3]
1.債務不履行の成否
Hは、Fの「山菜おこわ」を丙建物において無償で保管することをFと合意した。これは無償の寄託契約である。「和風だし」を目的物とする有償の寄託契約とは動機の部分で関係しているにすぎず、契約の内容とはなっていないので、「山菜おこわ」を目的物とする寄託は無償の寄託である。
そうであれば、Hは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物(「山菜おこわ」)を保管する義務を負う(第659条)。自己の財産を保管している建物には施錠をするのが通常であるから、丙建物の施錠を忘れていたために「山菜おこわ」が盗取されたというのは、この注意義務に反している。よってHの債務不履行となる。
2.Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなったことについての損害の賠償(以下「本件損害賠償」とする)を請求することができるか否か
Fは、Hに対し、本件損害賠償を請求することができる。
1で検討したようにHの債務不履行により「山菜おこわ」が500箱全て盗取され、Fはその返還を受けることができなかった。債務不履行に対する損害賠償は、原則として通常生ずべき損害に限られるが、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときには、その賠償を請求することができる(第416条第1項、第2項)。
Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなったことについての損害(本件損害)は第416条第2項の特別損害に当たる。平成24年1月12日のやり取りから、FはQとの間で、先行的に販売された「山菜おこわ」の評判がよいという条件付で、Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を販売するという契約が成立していたと考えられる。もし実際にそうなればFは「山菜おこわ」の販売から利益を得られていたはずなので、その契約がなくなってしまったことはFの損害に当たる。しかし、受寄していた目的物を返還できないとそれを超えた契約に影響を与えるということは通常生じないので特別損害に当たり、Hがその事情を予見し、又は予見することができたときに限り、Fはその賠償を請求することができる。
Hは平成24年1月22日に料亭「和南」にて行われたFとの会話を通じて、Hが受寄している先行販売用の「山菜おこわ」がその後のQ百貨店全店舗での取り扱いの条件となっていることを知った。もしその先行販売用の「山菜おこわ」がなくなってしまうと、評判がよいとか悪いとかの以前の話になり、FがQ百貨店全店舗での取り扱いをしてもらえなくなるであろうことは容易に予見できたはずである。そしてこの予見はHが注意義務に違反した平成24年1月24日の時点で可能であった。
以上より冒頭の結論となる。
*1 「Bが相続によりDから取得した」となるように「Dから」を挿入する。
以上
修正答案
以下民法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
(1)
この主張は認められない。その理由を以下で説明する。
1985年4月の時点ではCが実体上も登記上も甲土地を所有していた。その時点でCが死亡することにより、Cの子であるDとEが法定相続分(第900条第4号)に従い、甲土地の持分権を2分の1ずつ共有することとなる(第882条、第898条)。これと異なる遺言や遺産分割の存在は確認できない。そしてその2分の1の甲土地の持分権を1988年7月にBが相続によりDから取得した。
その後の1990年11月にBが甲土地をAに売るという売買契約が成立した。Aは契約成立日に代金を全額払っている。この時点でBは甲土地の持分権を2分の1だけ有しており、残りの2分の1はEが有している。他人物売買も有効でありBは甲土地全部の所有権をAに移転する義務を負う(第560条)が、Eの協力がなければそれは不可能である。そして本件でEの協力があった形跡はない。よってAは甲土地の2分の1の持分権は売買契約により取得するが、残りの2分の1の持分権については取得しない。相続によりこのAの立場は包括的に承継したFは、甲土地の所有権について、2分の1の持分権の限度について主張できるにすぎず、全部の所有権が自己にあるとの主張は認められない。
なお、Fが甲土地全部について自己を所有者とする登記をしていたとしてもこの結論に変わりはない。不動産の得喪については登記をしなければ第三者に対抗することができない(第177条)ところ、その第三者とは正当な利益を有する者に限定されると解釈するのが適切であり、Eが持分権を有している部分に関してFは正当な利益を有する者ではないからである。
(2)
下線を付した事実は、この取得時効の要件を論ずる上で法律上の意義を有する。この取得時効は第162条第1項に規定されており、そこでは「所有の意思をもって」という要件が挙げられている。この所有の意思は占有開始時を基準にして判断される。FはAと合わせて甲土地の占有が20年間継続したと主張するはずであるから、この場合はAの占有開始時が基準となる。下線を付した事実は、その基準となる時点で、Aが所有の意思をもっていたことを基礎づけるという法律上の意義を有する。占有者は所有の意思をもっていることが推定される(第186条第1項)が、下線を付した事実にはその推定を覆すことを妨げるという意義がある。また、第162条第1項は取得時効が成立する対象物として「他人の物」と規定しているので、下線を付した事実は甲土地がAにとって他人の物なのかそれとも自己の物なのかを決定する際にも意義を有している。長期に及ぶ事実状態を尊重するという取得時効の存在意義から考えると、仮に自己の物であったとしても取得時効を認めない理由はないとするのが判例である。
[設問2]
Gのする「和風だし」1000箱の引渡請求の全部が債権的には認められるが、そのうちの500箱についてはFの共有持分権が及ぶので、結果的には残りの500箱についてのみ引渡請求が認められる。
別紙の寄託契約書からだけでは、今回のように寄託物が滅失した場合についてどうすればよいかを一義的に決めることができないので、民法の規程を参考にしながら当事者の意思に沿うような解決が求められる。
FとH、GとHは、それぞれ別紙の内容の寄託契約を締結した。寄託契約書第1条によるとGはHに「和風だし」1000箱を寄託しており、同第6条により受寄者(H)は、寄託者(G)に対し、寄託者の寄託に係るものと同一数量のもの(「和風だし」1000箱)を返還する義務を負う。よって本来であれば、Gのする「和風だし」1000箱の引渡請求の全部がこの寄託契約に基づき認められることになる。
しかしHはFとも同様の寄託契約を結んでおり、Fの権利を侵害することを理由に、Gの請求に応ずることを拒んでいる。寄託者及び他の寄託者(FとG)が、混合保管をされた物について、それぞれ寄託した物の数量の割合(F:G=1:1)に応じ,寄託物の共有持分権を有する(寄託契約書第4条)ので、残存している1000箱についてはFとGが1:1の割合で共有持分権を有することとなる。そして各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(第251条)ので、Fの権利(共有持分権)を侵害するというHの主張は正当である。しかしGの引渡請求は共有物分割請求(第256条)だと解釈することができるので、Gが共有持分権を有している範囲(500箱)でそれが認められる。「和風だし」は1000箱まとまっていることに重要な意味があるものではなく小分けして売却することが予定されているものなので、このように共有物分割請求を認めるのが当事者の意思に適うと考えられる。
以上により冒頭で述べた結論となる。
[設問3]
1.債務不履行の成否
Hは、Fの「山菜おこわ」を丙建物において無償で保管することをFと合意し、それを丙建物に運び込んだので、寄託契約が成立している(第657条)。これは無償の寄託契約である。「和風だし」を目的物とする有償の寄託契約とは動機の部分で関係しているにすぎず、契約の内容とはなっていないので、「山菜おこわ」を目的物とする寄託は無償の寄託である。
そうであれば、Hは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物(「山菜おこわ」)を保管する義務を負う(第659条)。自己の財産を保管している建物には施錠をするのが通常であるから、丙建物の施錠を忘れていたために「山菜おこわ」が盗取されたというのは、この注意義務に反している。よってHの債務不履行となり、Fはこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(第415条)。
2.Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなったことについての損害の賠償(以下「本件損害賠償」とする)を請求することができるか否か
Fは、Hに対し、本件損害賠償を請求することができる。
1で検討したようにHの債務不履行により「山菜おこわ」が500箱全て盗取され、Fはその返還を受けることができなかったので、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。そこでFにHの債務不履行による損害が生じているかどうか、そして損害が生じているとすればどのような性質の損害であるかを順次検討する。
平成24年1月12日のやり取りから、FとQとの間で、先行的に販売された「山菜おこわ」の評判がよいという条件付で、Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を販売するという契約が成立していたと考えられる。条件付とはいってもQ百貨店のほうから声をかけたといった事情などを考慮すると、それが実現する蓋然性は高い。そしてもし実際にそうなればFは「山菜おこわ」の販売から利益を得られていたはずなので、その契約がなくなってしまったことはFの損害に当たる。多少の不確定要素は損害額の部分で反映させることもできるのだから、額はともかくとして損害が発生しているとするのが適切である。Qは先行販売用の「山菜おこわ」が盗取されてしまったことを受けてFの商品保管態勢が十分であるとはいえないとして、Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を販売するという話を取りやめた。こうした経緯から、Hの債務不履行によりFに損害が生じていると言える。
しかしながら、このような損害が発生するとは通常考えづらいので、Hにその責任を負わせるのは酷である。こうした事態に配慮しているのが第416条で、債務不履行に対する損害賠償は、原則として通常生ずべき損害に限られる(第416条第1項)が、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときには、その賠償を請求することができる(第416条第2項)と規定されている。その予見は、債務不履行をした者が、債務不履行時にすることができたかどうかで判断するのが責任主義の観点から妥当である。Q百貨店の全店舗で「山菜おこわ」を取り扱ってもらえなくなったことについての損害(本件損害)は第416条第2項の特別損害に当たり、Hが注意義務に違反して「山菜おこわ」を盗取されて時点でその事情を予見し、又は予見することができたときに限り、Fはその賠償を請求することができる。
Hは平成24年1月22日に料亭「和南」にて行われたFとの会話を通じて、Hが受寄している先行販売用の「山菜おこわ」がその後のQ百貨店全店舗での取り扱いの条件となっていることを知った。ある物を受寄する際には、それがどのような性質のものであり、どのような目的に用いられるかなどを知っておくはずであるという事情もある。もしその先行販売用の「山菜おこわ」がなくなってしまうと、評判がよいとか悪いとかの以前の話になり、FがQ百貨店全店舗での取り扱いをしてもらえなくなるであろうことは容易に予見できたはずである。そしてこの予見はHが注意義務に違反した平成24年1月24日の時点で可能であった。
以上より冒頭の結論となる。
以上
感想
[設問2]はどう論じたらよいかわからず悩んだ末に、出題者から求められていない供託という記述をしてしまいました。[設問1]と[設問3]は一応の水準くらいには達していたのではないかと思いますが、不十分な点が多々あったので、それを修正しました。