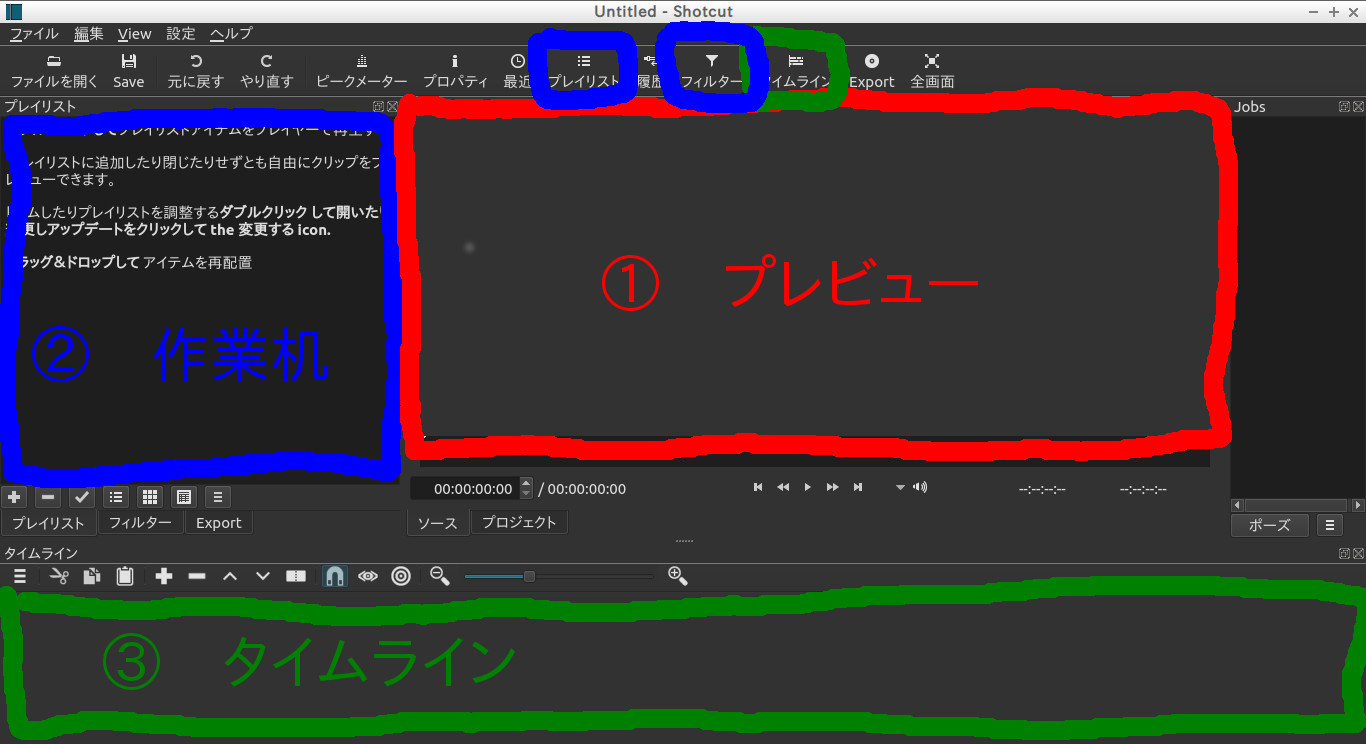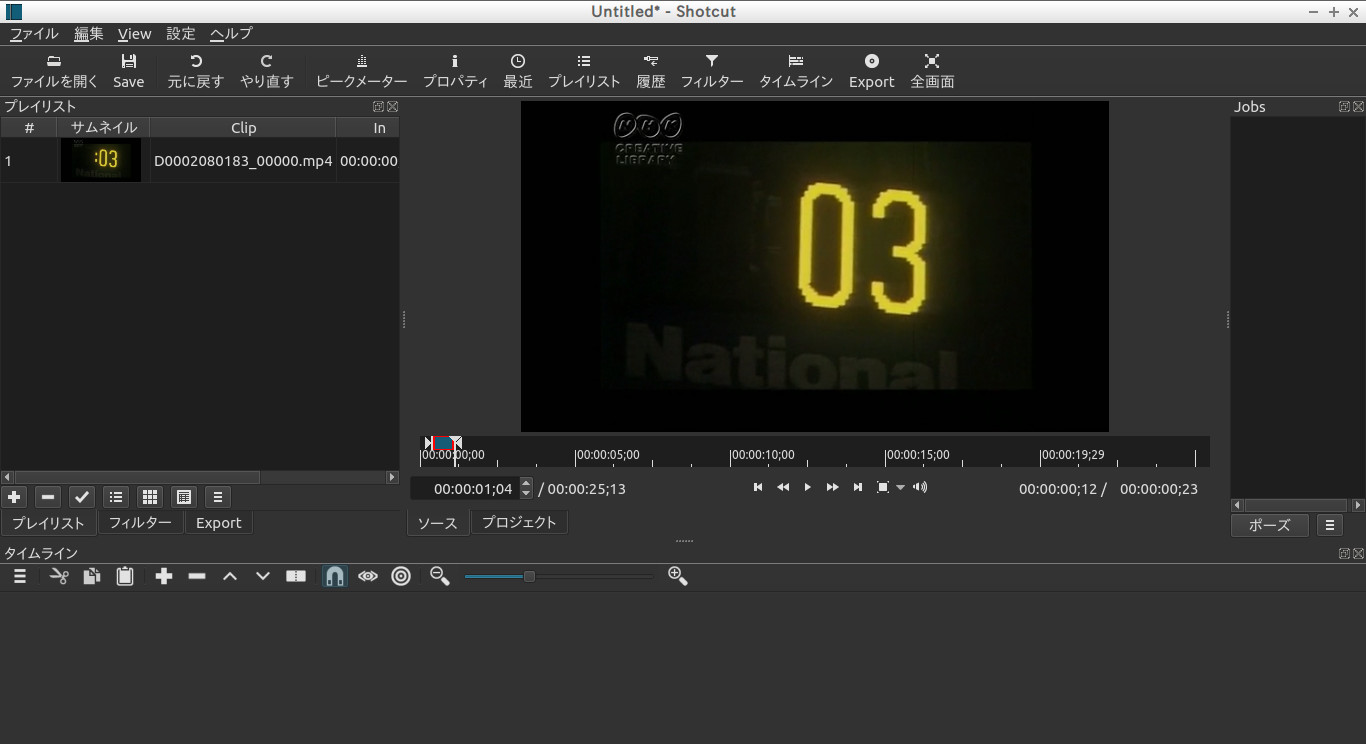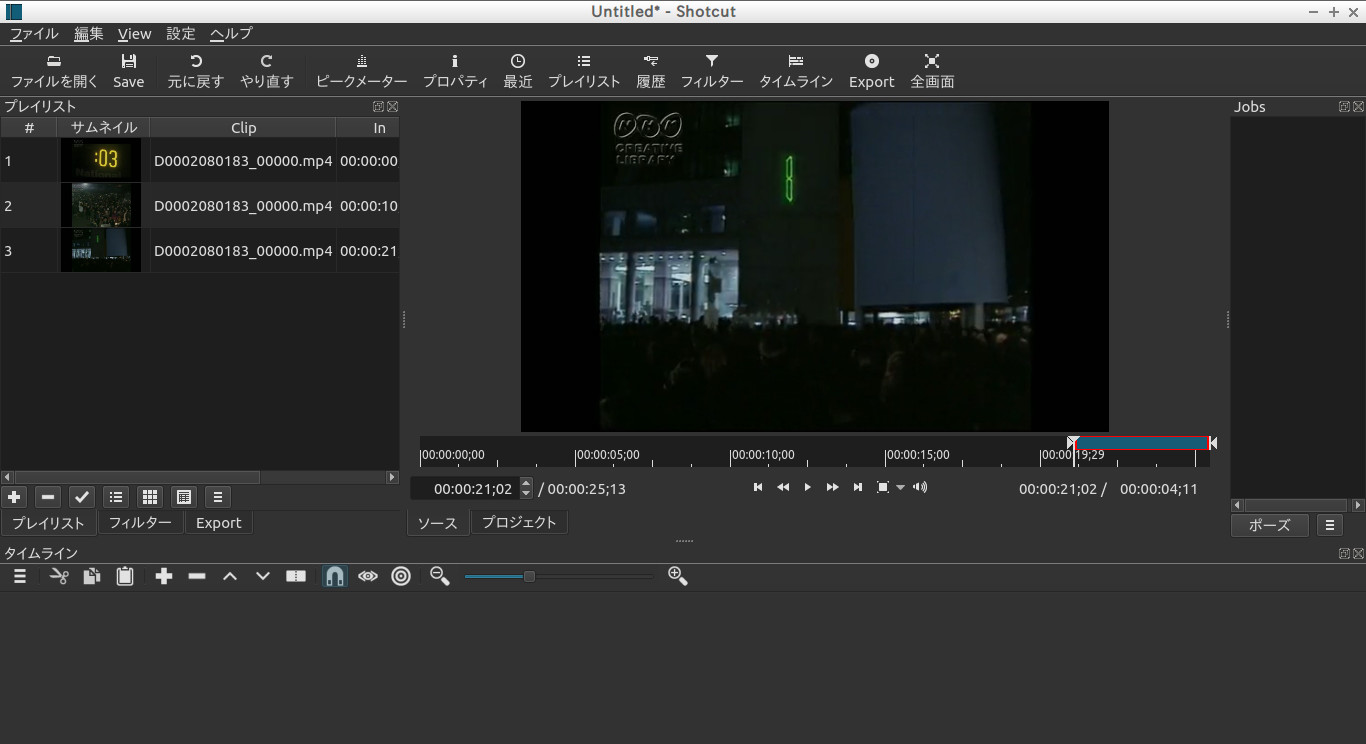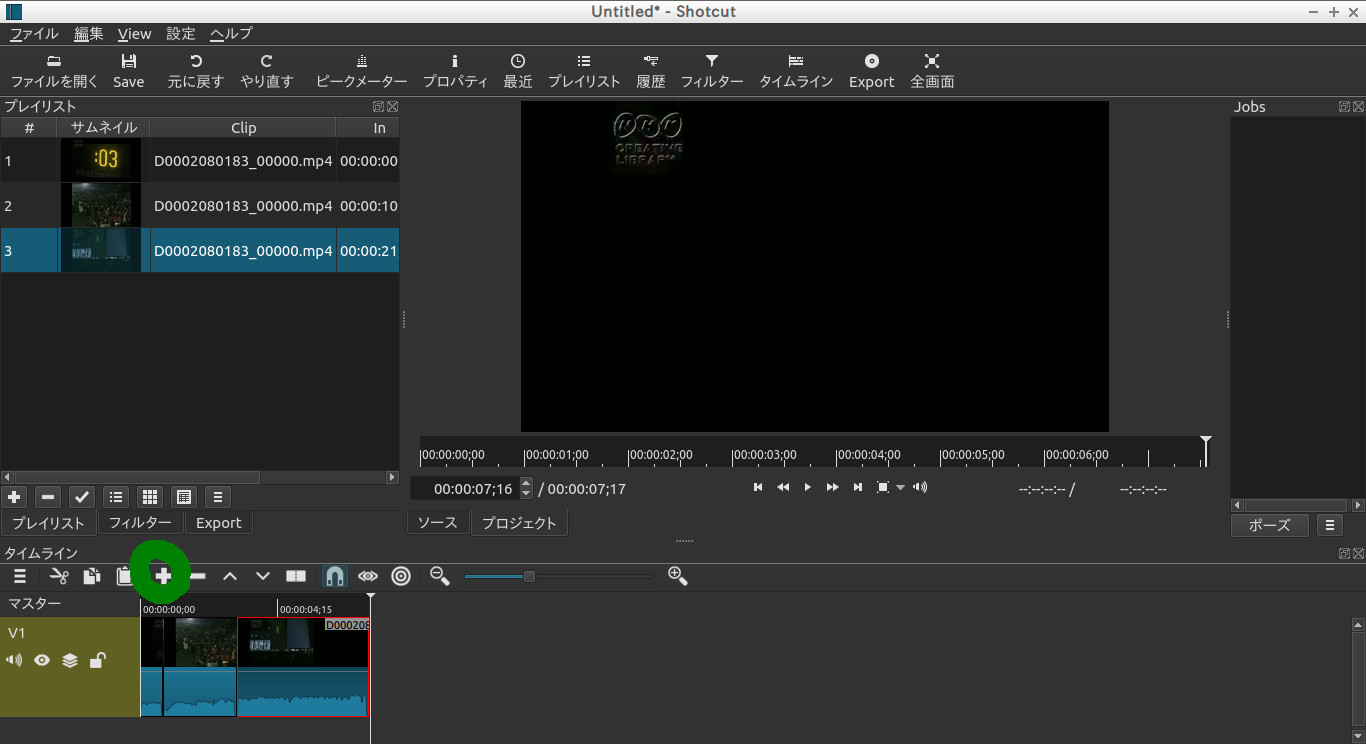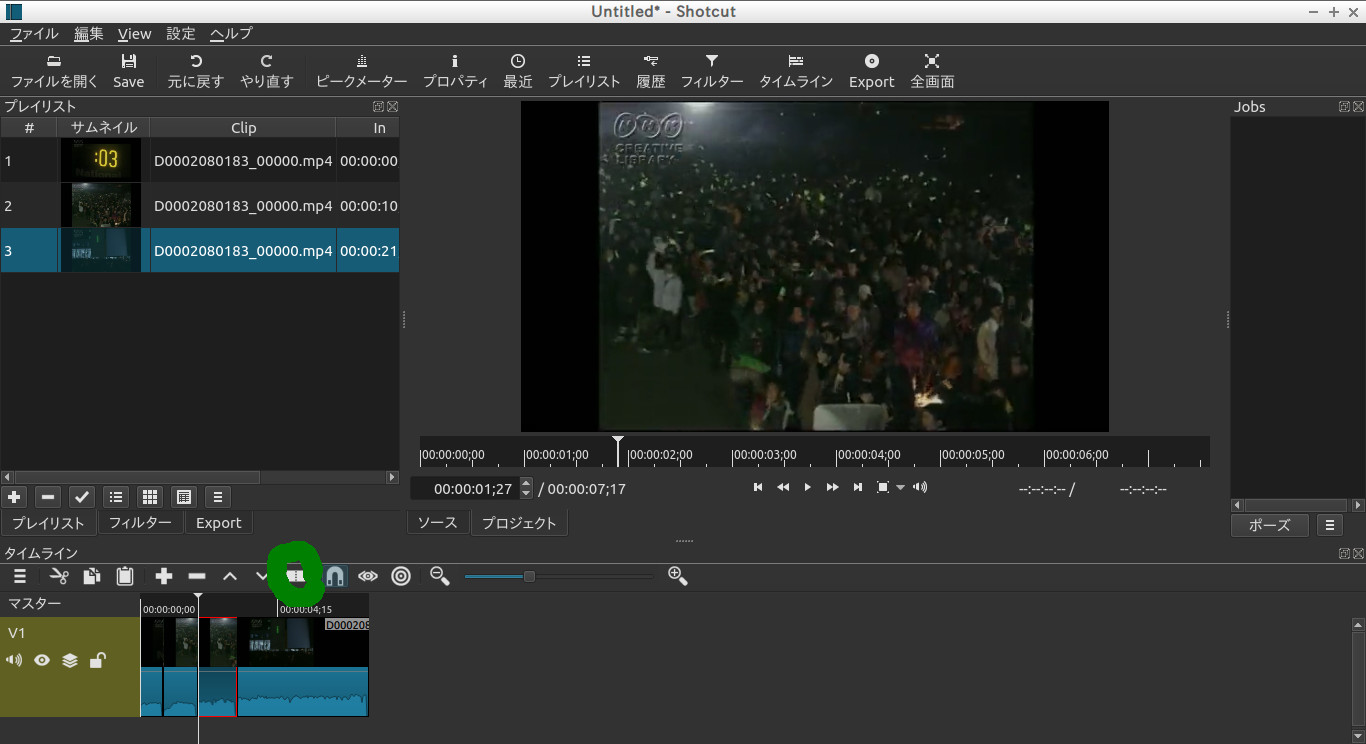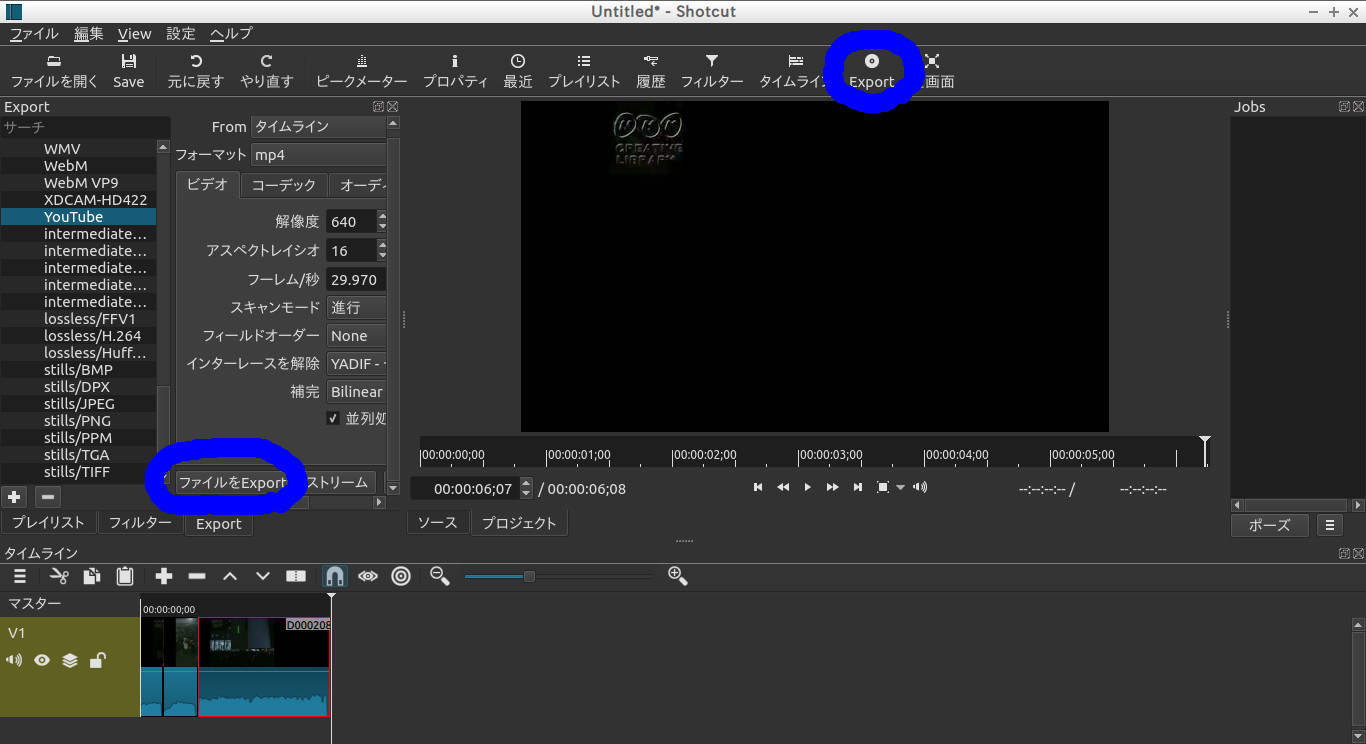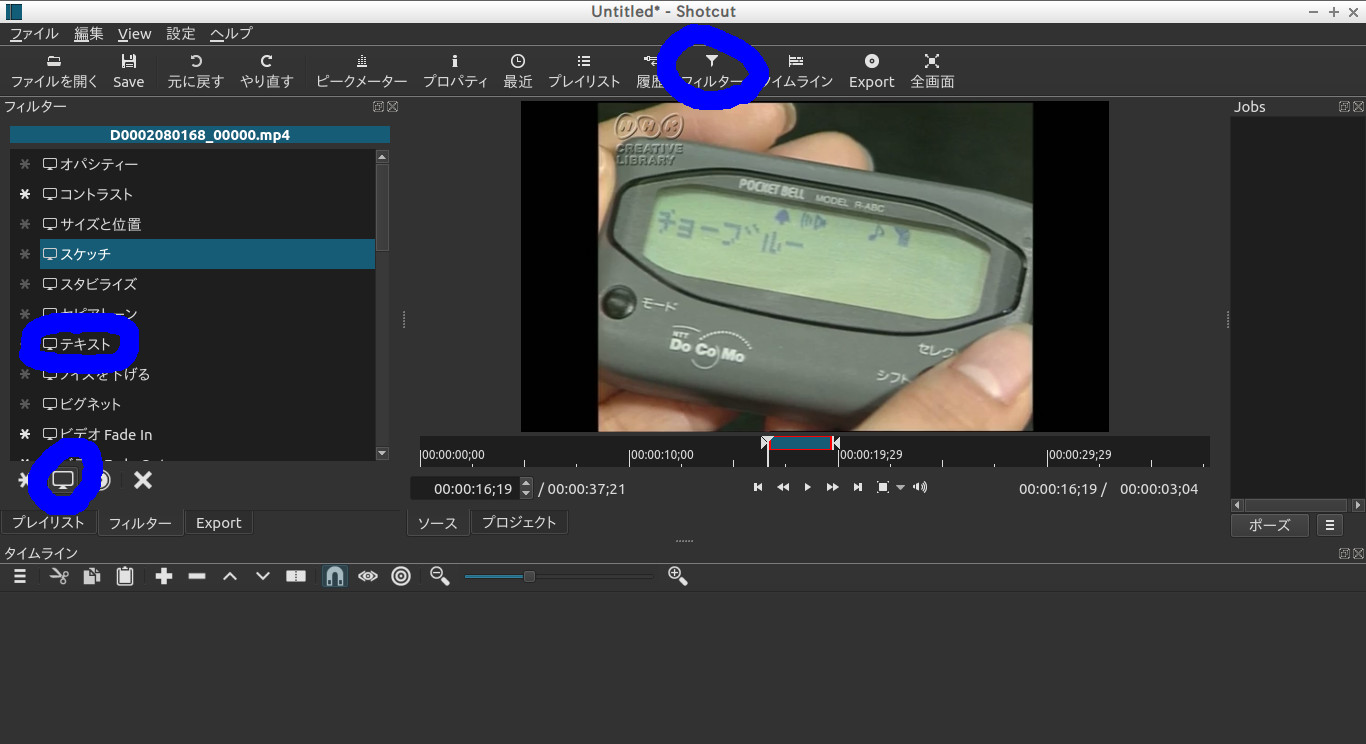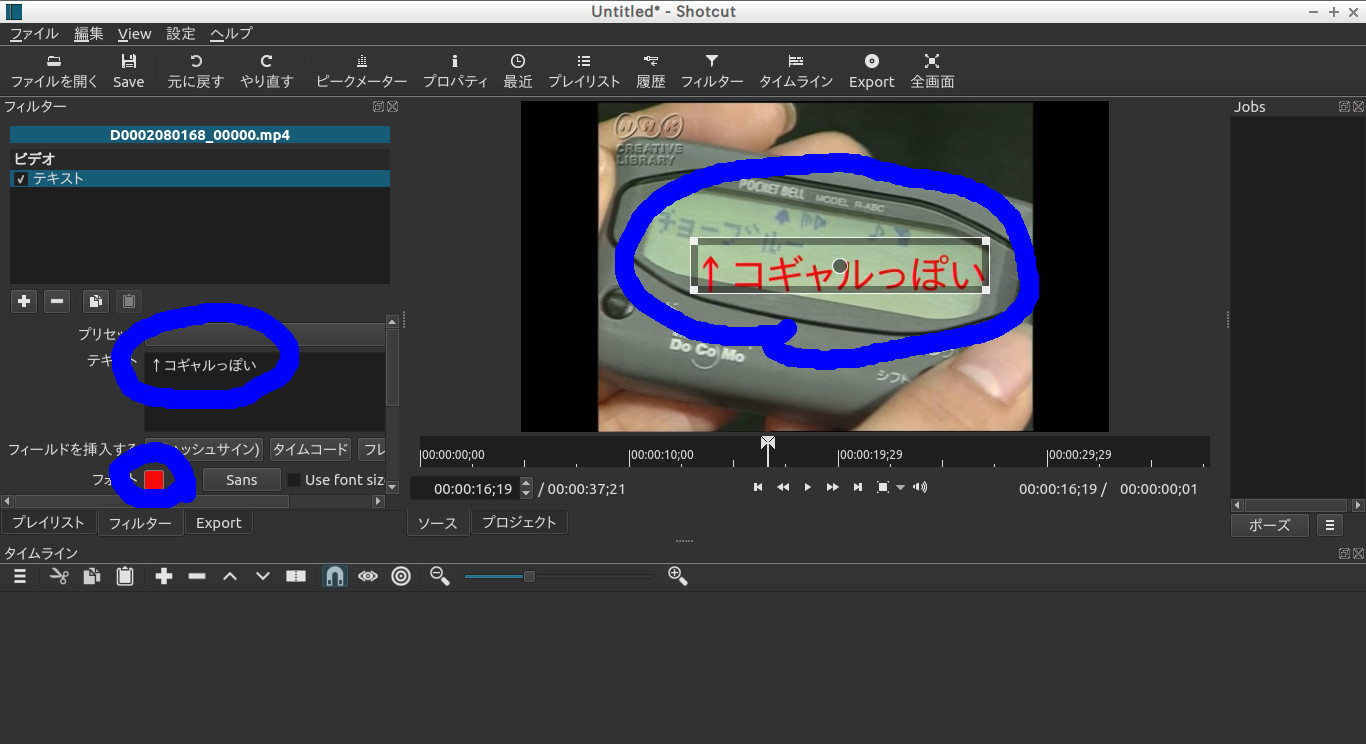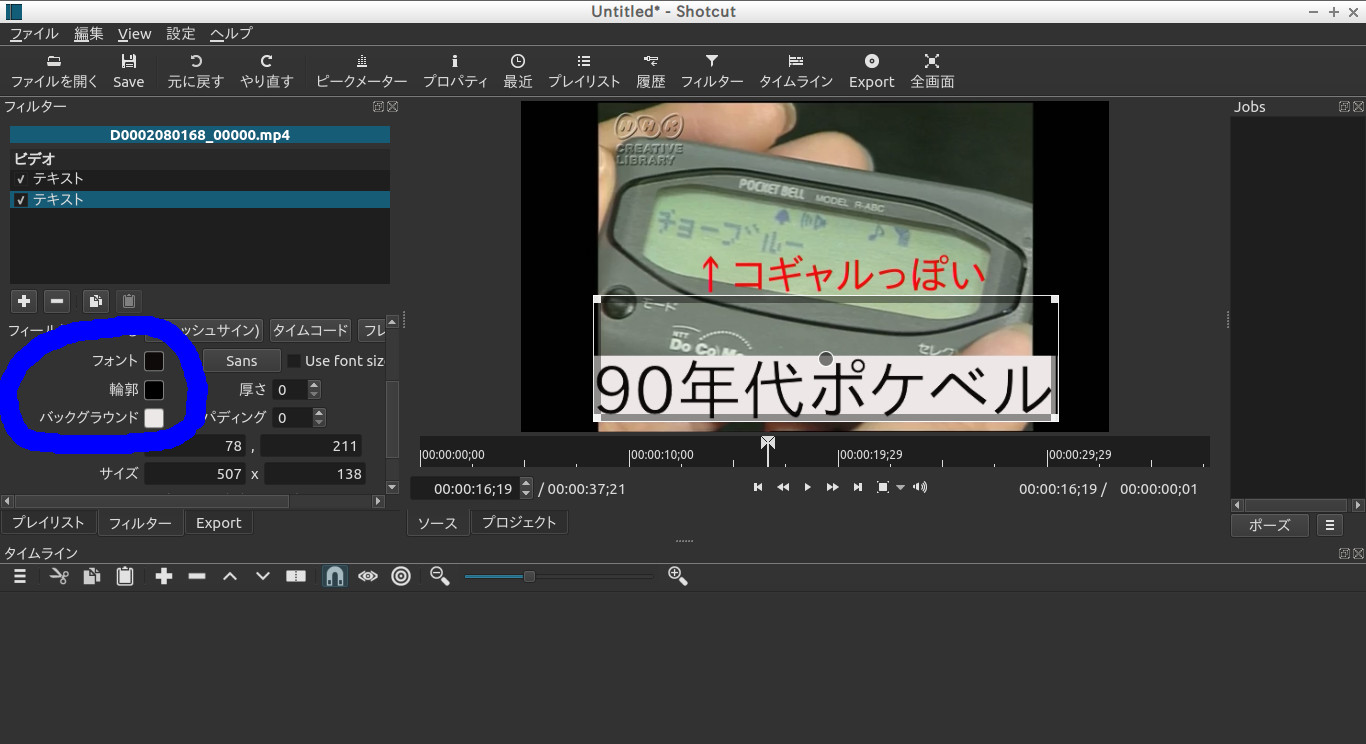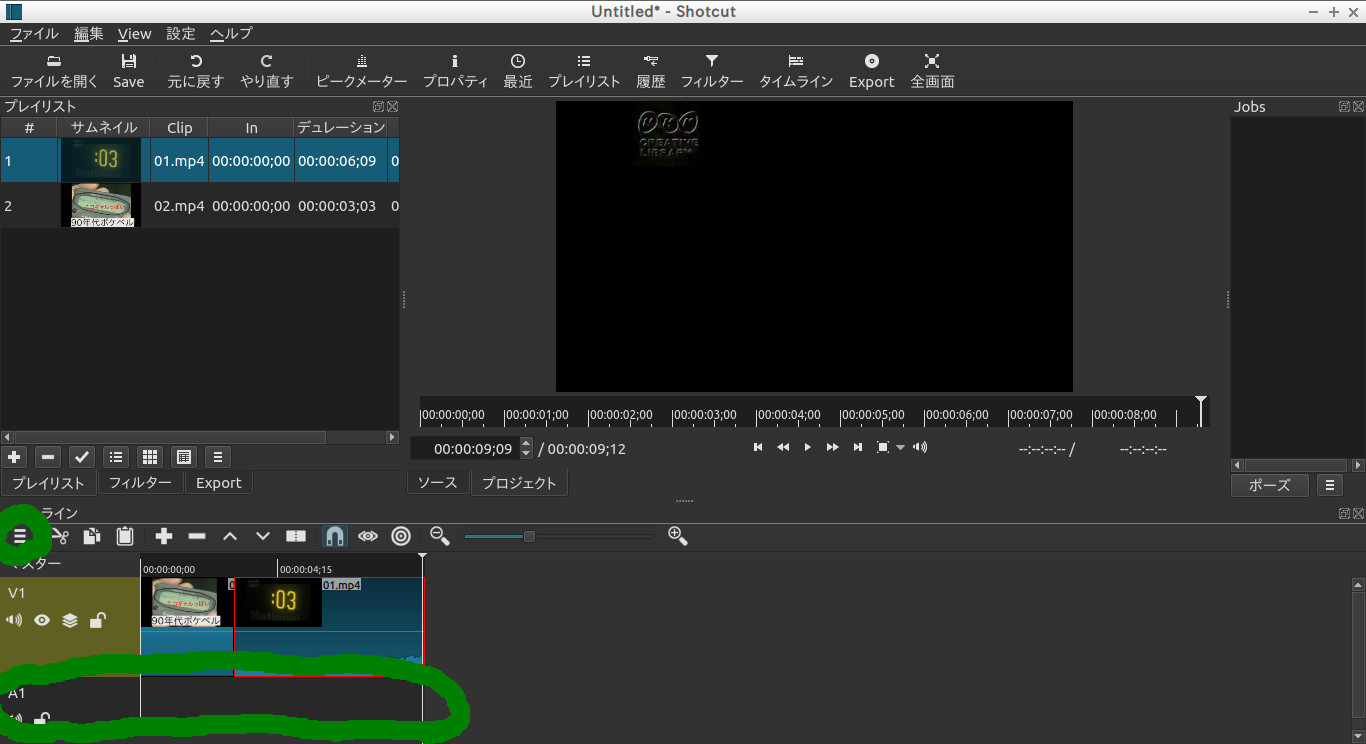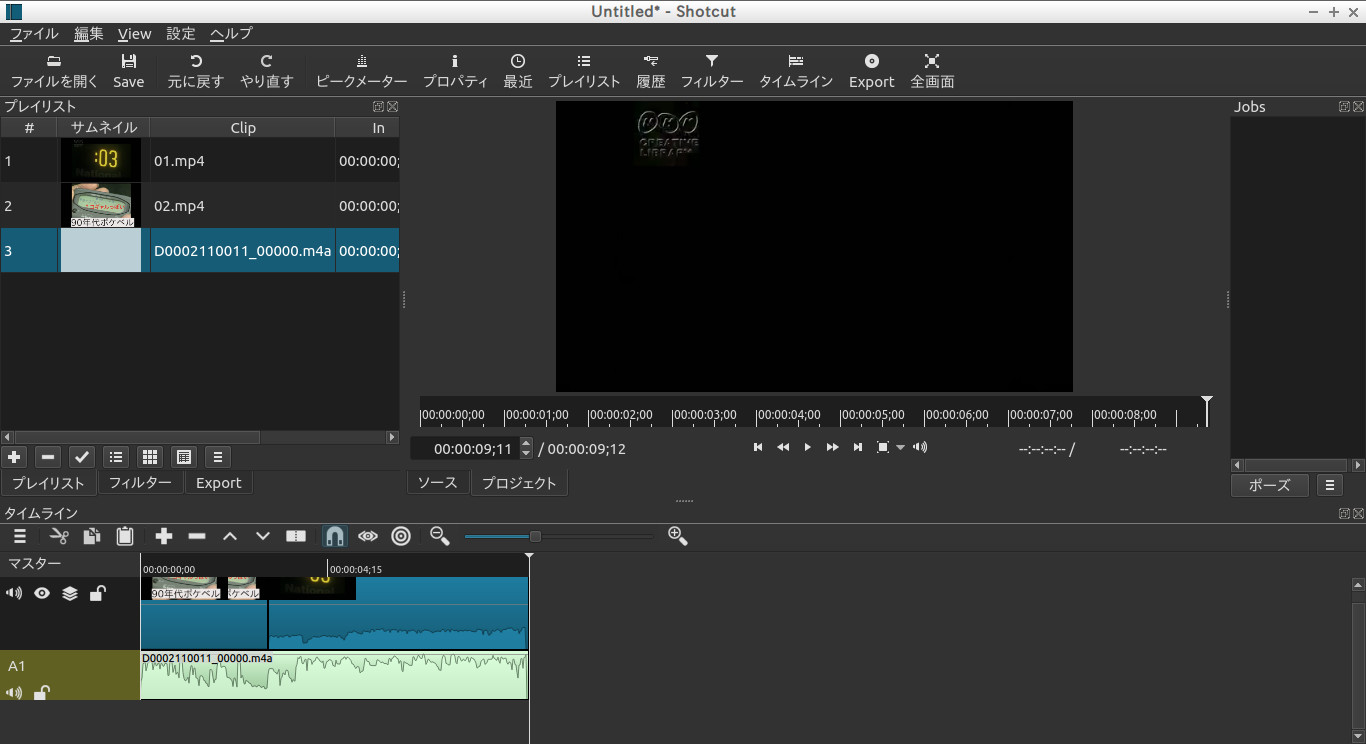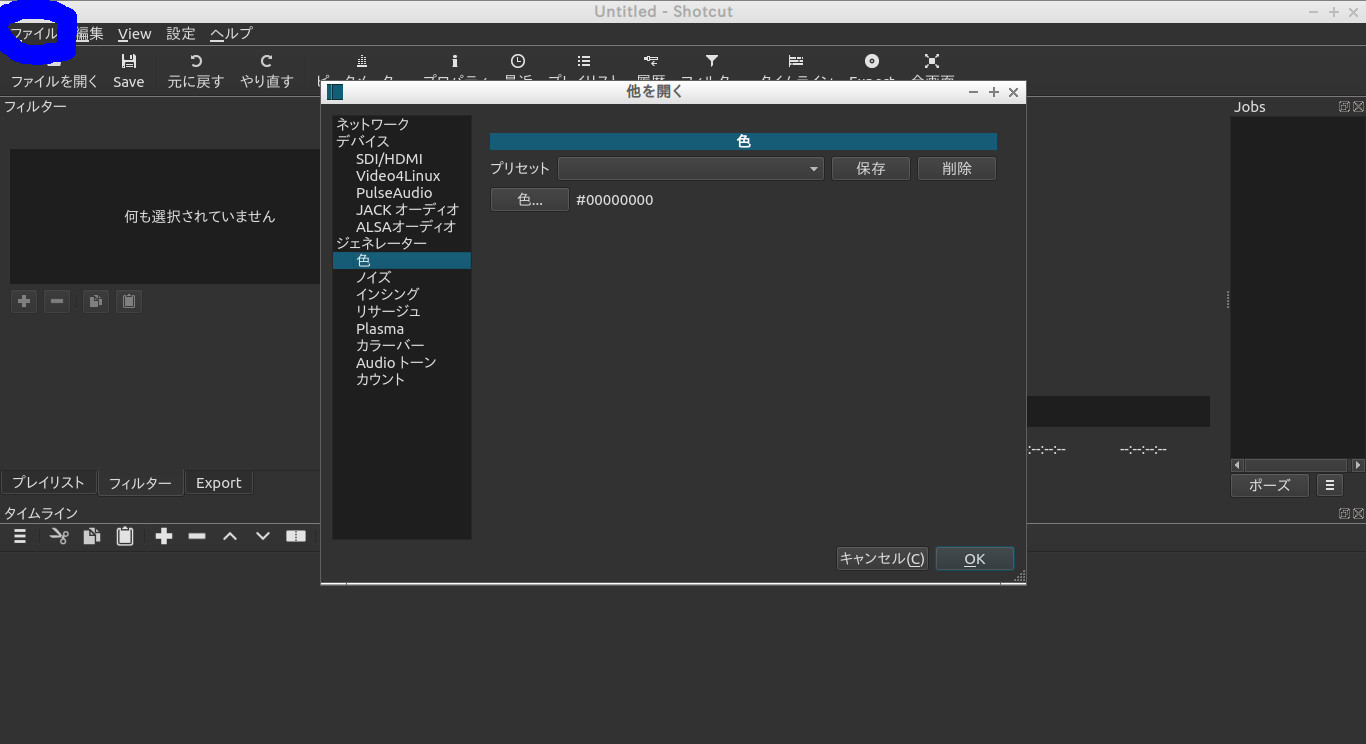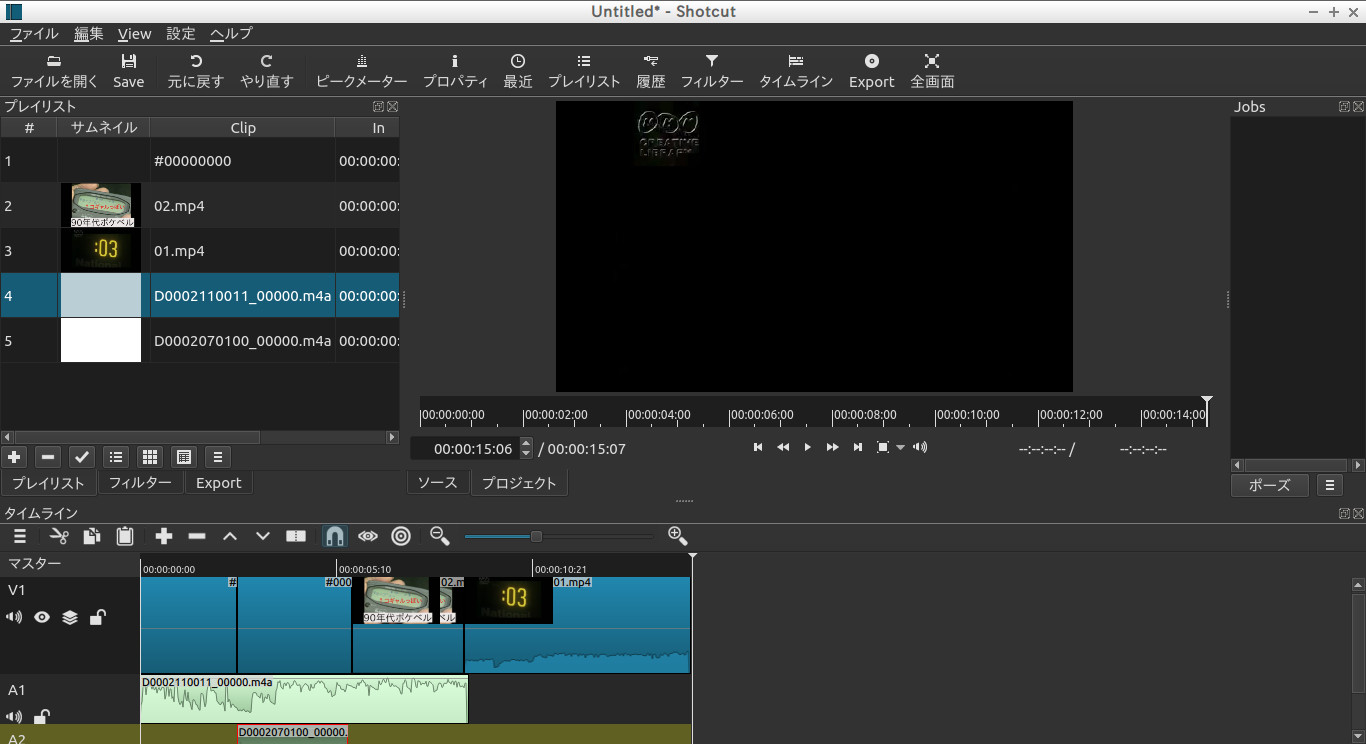非訴事件
憲法八二条は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」旨規定する。そして如何なる事項を公開の法廷における対審及び判決によつて裁判すべきかについて、憲法は何ら規定を設けていない。しかし、法律上の実体的権利義務自体につき争があり、これを確定するには、公開の法廷における対審及び判決によるべきものと解する。けだし、法律上の実体的権利義務自体を確定することが固有の司法権の主たる作用であり、かかる争訟を非訟事件手続または審判事件手続により、決定の形式を以て裁判することは、前記憲法の規定を回避することになり、立法を以てしても許されざるところであると解すべきであるからである。
家事審判法九条一項乙類は、夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する事件を婚姻費用の分担、財産分与、扶養、遺産分割等の事件と共に、審判事項として審判手続により審判の形式を以て裁判すべき旨規定している。その趣旨とするところは、夫婦同居の義務その他前記の親族法、相続法上の権利義務は、多分に倫理的、道義的な要素を含む身分関係のものであるから、一般訴訟事件の如く当事者の対立抗争の形式による弁論主義によることを避け、先ず当事者の協議により解決せしめるため調停を試み、調停不成立の場合に審判手続に移し、非公開にて審理を進め、職権を以て事実の探知及び必要な証拠調を行わしめるなど、訴訟事件に比し簡易迅速に処理せしめることとし、更に決定の一種である審判の形式により裁判せしめることが、かかる身分関係の事件の処理としてふさわしいと考えたものであると解する。しかし、前記同居義務等は多分に倫理的、道義的な要素を含むとはいえ、法律上の実体的権利義務であることは否定できないところであるから、かかる権利義務自体を終局的に確定するには公開の法廷における対審及び判決によつて為すべきものと解せられる(旧人事訴訟手続法〔家事審判法施行法による改正前のもの〕一条一項参照)。従つて前記の審判は夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく、これら実体的権利義務の存することを前提として、例えば夫婦の同居についていえば、その同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定める処分であり、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解するのが相当である。けだし、民法は同居の時期、場所、態様について一定の基準を規定していないのであるから、家庭裁判所が後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使してその具体的内容を形成することが必要であり、かかる裁判こそは、本質的に非訟事件の裁判であつて、公開の法廷における対審及び判決によつて為すことを要しないものであるからである。すなわち、家事審判法による審判は形成的効力を有し、また、これに基づき給付を命じた場合には、執行力ある債務名義と同一の効力を有するものであることは同法一五条の明定するところであるが、同法二五条三項の調停に代わる審判が確定した場合には、これに確定判決と同一の効力を認めているところより考察するときは、その他の審判については確定判決と同一の効力を認めない立法の趣旨と解せられる。然りとすれば、審判確定後は、審判の形成的効力については争いえないところであるが、その前提たる同居義務等自体については公開の法廷における対審及び判決を求める途が閉ざされているわけではない。従つて、同法の審判に関する規定は何ら憲法八二条、三二条に牴触するものとはいい難く、また、これに従つて為した原決定にも違憲の廉はない。それ故、違憲を主張する論旨は理由がなく、その余の論旨は原決定の違憲を主張するものではないから、特別抗告の理由にあたらない。
忌避
原審における裁判長たる裁判官が、原審における被上告組合の訴訟代理人の女壻であるからといつて、右の事実は民訴三五条所定事項に該当せず、又これがため直ちに民訴三七条にいわゆる裁判官につき裁判の公正を妨ぐべき事情があるものとはいえないから、所論は理由がない。
死者名義訴訟の承継
本件記録によると、(一)被上告人の先代Dから昭和四三年一二月二七日適法に訴訟委任を受けた弁護士佐治良三ほか四名の訴訟代理人が、同月三〇日Dが死亡したことを知らずに、昭和四四年三月一一日亡Dを原告、上告人を被告と表示した本件訴状を第一審裁判所へ提出し、これが上告人に送達されたこと、(二)同年五月一三日亡Dの相続人たる被上告人ほか二名からの申立により第一審裁判所が被上告人ほか二名の原告としての訴訟承継を認めて審理判決したこと、(三)原審において、遺産分割の結果被上告人だけが本件土地の権利を承継したので被上告人以外の当事者が訴を取り下げ、上告人がこれに同意したこと、がそれぞれ認められる。このような事実関係のもとにおいては、民訴法八五条【引用者注:現五八条】、二〇八条【引用者注:現一二四条】の規定を類推適用して、本訴提起は適法なものであり、亡Dの相続人において本訴を承継したものと解するのが相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、叙上と反する独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。
法人格のない団体(権利能力なき社団)
最判昭和39.10.15(引揚者更生生活協同組合連盟杉並支部事件)
法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴四六条【引用者注:現二九条】がこれについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。しかして、このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて登記の場合、権利者自体の名を登記することを要し、権利能力なき社団においては、その実質的権利者たる構成員全部の名を登記できない結果として、その代表者名義をもつて不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。)。
訴訟代理権と和解
原審が当事者間に争いのない事実として確定したところによれば、本件においていわゆる前事件(徳島地方裁判所富岡支部昭和三元年(ワ)第一八号貸金請求事件)において上告人が訴訟代理人弁護士埴渕可雄に対し民訴八一条二項【引用者注:現五五条二項】所定の和解の権限を授与し、かつ、右委任状(書面)が前事件の裁判所に提出されているというのである。また原審が適法に認定したところによれば、右前事件は、前事件原告(本件被上告人先代)Dから前事件被告(本件控訴人、上告人)に対する金銭債権に関する事件であり、この弁済期日を延期し、かつ分割払いとするかわりに、その担保として上告人所有の不動産について、被上告人先代のために抵当権の設定がなされたものであつて、このような抵当権の設定は、訴訟物に関する互譲の一方法としてなされたものであることがうかがえるのである。しからば、右のような事実関係の下においては、前記埴渕弁護士が授権された和解の代理権限のうちに右抵当権設定契約をなす権限も包含されていたものと解するのが相当であつて、これと同趣旨に出た原判決の判断は、正当であり、この点に関する原判決の説示はこれを是認することができる。
形式的形成訴訟
しかしながら、境界確定を求める訴えは、公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合において、その境界が事実上不明なため争いがあるときに、裁判によって新たにその境界を定めることを求める訴えであって、裁判所が境界を定めるに当たっては、当事者の主張に拘束されず、控訴された場合も民訴法三八五条【引用者注:現三〇四条】の不利益変更禁止の原則の適用もない(最高裁昭和三七年(オ)第九三八号同三八年一〇月一五日第三小法廷判決・民集一七巻九号一二二〇頁参照)。右訴えは、もとより土地所有権確認の訴えとその性質を異にするが、その当事者適格を定めるに当たっては、何ぴとをしてその名において訴訟を追行させ、また何ぴとに対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決すべきであるから、相隣接する土地の各所有者が、境界を確定するについて最も密接な利害を有する者として、その当事者となるのである。したがって、右の訴えにおいて、甲地のうち境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合においても、甲乙両地の各所有者は、境界に争いがある隣接土地の所有者同士という関係にあることに変わりはなく、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。なお、隣接地の所有者が他方の土地の一部を時効取得した場合も、これを第三者に対抗するためには登記を具備することが必要であるところ、右取得に係る土地の範囲は、両土地の境界が明確にされることによって定まる関係にあるから、登記の前提として時効取得に係る土地部分を分筆するためにも両土地の境界の確定が必要となるのである(最高裁昭和五七年(オ)第九七号同五八年一〇月一八日第三小法廷判決・民集三七巻八号一一二一頁参照)。
将来の給付の訴え
民訴法二二六条【引用者注:現一三五条】はあらかじめ請求する必要があることを条件として将来の給付の訴えを許容しているが、同条は、およそ将来に生ずる可能性のある給付請求権のすべてについて前記の要件のもとに将来の給付の訴えを認めたものではなく、主として、いわゆる期限付請求権や条件付請求権のように、既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか又は容易に立証しうる別の一定の事実の発生にかかつているにすぎず、将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により右請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないと考えられるようなものについて、例外として将来の給付の訴えによる請求を可能ならしめたにすぎないものと解される。このような規定の趣旨に照らすと、継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権についても、例えば不動産の不法占有者に対して明渡義務の履行完了までの賃料相当額の損害金の支払を訴求する場合のように、右請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに、右請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては、債務者による占有の廃止、新たな占有権原の取得等のあらかじめ明確に予測しうる事由に限られ、しかもこれについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない点において前記の期限付債権等と同視しうるような場合には、これにつき将来の給付の訴えを許しても格別支障があるとはいえない。しかし、たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であつても、それが現在と同様に不法行為を構成するか否か及び賠償すべき損害の範囲いかん等が流動性をもつ今後の複雑な事実関係の展開とそれらに対する法的評価に左右されるなど、損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができるとともに、その場合における権利の成立要件の具備については当然に債権者においてこれを立証すべく、事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものについては、前記の不動産の継続的不法占有の場合とはとうてい同一に論ずることはできず、かかる将来の損害賠償請求権については、冒頭に説示したとおり、本来例外的にのみ認められる将来の給付の訴えにおける請求権としての適格を有するものとすることはできないと解するのが相当である。
確認の利益
よつて按ずるに、いわゆる遺言無効確認の訴は、遺言が無効であることを確認するとの請求の趣旨のもとに提起されるから、形式上過去の法律行為の確認を求めることとなるが、請求の趣旨がかかる形式をとつていても、遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは、適法として許容されうるものと解するのが相当である。けだし、右の如き場合には、請求の趣旨を、あえて遺言から生ずべき現在の個別的法律関係に還元して表現するまでもなく、いかなる権利関係につき審理判断するかについて明確さを欠くことはなく、また、判決において、端的に、当事者間の紛争の直接的な対象である基本的法律行為たる遺言の無効の当否を判示することによつて、確認訴訟のもつ紛争解決機能が果たされることが明らかだからである。
形成の訴えの利益の喪失
株主総会決議取消の訴えのような形成の訴えは、法律に規定のある場合に限つて許される訴えであるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴えの利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を喪失するに至る場合のあることは否定しえないところである。しかして、被上告人らの上告人に対する本訴請求は、昭和四五年一一月二八日に開催された上告会社の第四二回定時株主総会における「昭和四五年四月一日より同年九月三〇日に至る第四二期営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分案を原案どおり承認する」旨の本件決議について、その手続に瑕疵があることを理由として取消を求めるものであるところ、その勝訴の判決が確定すれば、右決議は初めに遡つて無効となる結果、営業報告書等の計算書類については総会における承認を欠くことになり、また、右決議に基づく利益処分もその効力を有しないことになつて、法律上再決議が必要となるものというべきであるから、その後に右議案につき再決議がされたなどの特別の事情かない限り、右決議取消を求める訴えの利益が失われることはないものと解するのが相当である。
そこで、叙上の見地に立つて、本件につきかかる特別の事情が存するか否かについて検討する。この点に関し、論旨は、本件決議が取り消されたとしても、右決議ののち第四三期ないし第五四期の各定時株主総会において各期の決算案は承認されて確定しており、右決議取消の効果は、右第四三期ないし第五四期の決算承認決議の効力に影響を及ぼすものではないから、もはや本件決議取消の訴えはその利益を欠くに至つたというのであるが、株主総会における計算書類等の承認決議がその手続に法令違反等があるとして取消されたときは、たとえ計算書類等の内容に違法、不当がない場合であつても、右決議は既往に遡つて無効となり、右計算書類等は未確定となるから、それを前提とする次期以降の計算書類等の記載内容も不確定なものになると解さざるをえず、したがつて、上告会社としては、あらためて取消された期の計算書類等の承認決議を行わなければならないことになるから、所論のような事情をもつて右特別の事情があるということはできない。また、論旨は、修正動議無視の瑕疵は、その後右動議にいう水俣病補償積立金及び水俣病対策積立金以上の額の水俣病の補償金及び対策費が支出され、右動議の目的がすでに達成されているので、右瑕疵は治癒され訴えの利益は失われたというが、被上告人らの上告人に対する本訴請求は、株主の入場制限及び修正動議無視という株主総会決議の手続的瑕疵を主張してその効力の否認を求めるものであるから、右修正動議の内容が後日実現されたということがあつても、そのことをもつて右特別の事情と認めるに足りず、他に右特別の事情を認めるに足る事実関係のない本件においては、訴えの利益を欠くに至つたものと解することはできない。これと同旨の原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
任意的訴訟担当
ところで、訴訟における当事者適格は、特定の訴訟物について、何人をしてその名において訴訟を追行させ、また何人に対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決せられるべきものである。したがつて、これを財産権上の請求における原告についていうならば、訴訟物である権利または法律関係について管理処分権を有する権利主体が当事者適格を有するのを原則とするのである。しかし、それに限られるものでないのはもとよりであつて、たとえば、第三者であつても、直接法律の定めるところにより一定の権利または法律関係につき当事者適格を有することがあるほか、本来の権利主体からその意思に基づいて訴訟追行権を授与されることにより当事者適格が認められる場合もありうるのである。
そして、このようないわゆる任意的訴訟信託については、民訴法上は、同法四七条【引用者注:現三七条】が一定の要件と形式のもとに選定当事者の制度を設けこれを許容しているのであるから、通常はこの手続によるべきものではあるが、同条は、任意的な訴訟信託が許容される原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続による以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。すなわち、任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法一一条が訴訟行為を為さしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、当該訴訟信託がこのような制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合には許容するに妨げないと解すべきである。
そして、民法上の組合において、組合規約に基づいて、業務執行組合員に自己の名で組合財産を管理し、組合財産に関する訴訟を追行する権限が授与されている場合には、単に訴訟追行権のみが授与されたものではなく、実体上の管理権、対外的業務執行権とともに訴訟追行権が授与されているのであるから、業務執行組合員に対する組合員のこのような任意的訴訟信託は、弁護士代理の原則を回避し、または信託法一一条の制限を潜脱するものとはいえず、特段の事情のないかぎり、合理的必要を欠くものとはいえないのであつて、民訴法四七条による選定手続によらなくても、これを許容して妨げないと解すべきである。したがつて、当裁判所の判例(昭和三四年(オ)第五七七号・同三七年七月一三日言渡第二小法廷判決・民集一六巻八号一五一六頁)は、右と見解を異にする限度においてこれを変更すべきものである。
そして、本件の前示事実関係は記録によりこれを肯認しうるところ、その事実関係によれば、民法上の組合たる前記企業体において、組合規約に基づいて、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行する権限を与えられた業務執行組合員たる上告人は、組合財産に関する訴訟につき組合員から任意的訴訟信託を受け、本訴につき自己の名で訴訟を追行する当事者適格を有するものというべきである。しかるに、これと異なる見解のもとに上告人が右の当事者適格を欠くことを理由に本件訴を不適法として却下した原判決は、民訴法の解釈を誤るもので、この点に関する論旨は理由がある。したがつて、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、更に本件を審理させるためこれを原審に差し戻すこととする。
相殺の抗弁と重複起訴の禁止
1 民訴法一四二条(旧民訴法二三一条)が係属中の事件について重複して訴えを提起することを禁じているのは、審理の重複による無駄を避けるとともに、同一の請求について異なる判決がされ、既判力の矛盾抵触が生ずることを防止する点にある。そうすると、自働債権の成立又は不成立の判断が相殺をもって対抗した額について既判力を有する相殺の抗弁についても、その趣旨を及ぼすべきことは当然であって、既に係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することが許されないことは、原審の判示するとおりである(前記平成三年一二月一七日第三小法廷判決参照)。
2 しかしながら、他面、一個の債権の一部であっても、そのことを明示して訴えが提起された場合には、訴訟物となるのは右債権のうち当該一部のみに限られ、その確定判決の既判力も右一部のみについて生じ、残部の債権に及ばないことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三五年(オ)第三五九号同三七年八月一〇日第二小法廷判決・民集一六巻八号一七二〇頁参照)。この理は相殺の抗弁についても同様に当てはまるところであって、一個の債権の一部をもってする相殺の主張も、それ自体は当然に許容されるところである。
3 もっとも、一個の債権が訴訟上分割して行使された場合には、実質的な争点が共通であるため、ある程度審理の重複が生ずることは避け難く、応訴を強いられる被告や裁判所に少なからぬ負担をかける上、債権の一部と残部とで異なる判決がされ、事実上の判断の抵触が生ずる可能性もないではない。そうすると、右2のように一個の債権の一部について訴えの提起ないし相殺の主張を許容した場合に、その残部について、訴えを提起し、あるいは、これをもって他の債権との相殺を主張することができるかについては、別途に検討を要するところであり、残部請求等が当然に許容されることになるものとはいえない。
しかし、こと相殺の抗弁に関しては、訴えの提起と異なり、相手方の提訴を契機として防御の手段として提出されるものであり、相手方の訴求する債権と簡易迅速かつ確実な決済を図るという機能を有するものであるから、一個の債権の残部をもって他の債権との相殺を主張することは、債権の発生事由、一部請求がされるに至った経緯、その後の審理経過等にかんがみ、債権の分割行使による相殺の主張が訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存する場合を除いて、正当な防御権の行使として許容されるものと解すべきである。
したがって、一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許されるものと解するのが相当である。
表見法理
ところで、所論は、まず、民法一〇九条、商法二六二条の規定により被上告会社についてDにその代表権限を肯認すべきであるとする。しかし、民法一〇九条および商法二六二条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図つた規定である商法四二条一項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがつて、本訴において、Dには被上告会社の代表者としての資格はなく、同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。
そうして、右のような場合、訴状は、民訴法五八条【引用者注:現三七条】、一六五条【引用者注:現一〇二条】により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたDに宛てて送達されたものであることが認められ、Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもつてしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。したがつて、このような場合には、裁判所としては、民訴法二二九条二項【引用者注:現一三八条】、二二八条一項【引用者注:現一三七条】により、上告人に対し訴状の補正を命じ、また、被上告会社に真正な代表者のない場合には、上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、正当な権限を有する者に対しあらためて訴状の送達をすることを要するのであつて、上告人において右のような補正手続をとらない場合にはじめて裁判所は上告人の訴を却下すべきものである。そして、右補正命令の手続は、事柄の性質上第一審裁判所においてこれをなすべきものと解すべきであるから、このような場合、原審としては、第一審判決を取り消し、第一審裁判所をして上告人に対する前記補正命令をさせるべく、本件を第一審裁判所に差し戻すべきものと解するを相当とする。しかるに、原審がDに被上告会社の代表権限がない事実よりただちに本件訴を不適法として却下したことは、民訴法の解釈を誤るものであつて、この点に関する論旨は理由がある。
信義則
右の事実関係に照らすと、被上告人が、上告人の主張に沿つて、本件売買契約の無効、取消、解除の主張を撤回し、右売買契約上の自己の義務を完全に履行したうえ、再反訴請求に及んだところ、その後に上告人は、一転して、さきに自ら否認し、そのため被上告人が撤回した取消、解除の主張を本件売買契約の効力を争うための防禦方法として提出したものであつて、上告人の右のような態度は、訴訟上の信義則に著しく反し許されないと解するのが、相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張するか、原判決の結論に影響を及ぼさない部分を非難するものに帰し、採用することができない。
釈明義務
そこで、検討するのに、本件においては、公図の記載等によれば、本件係争部分がすべて上告人所有の本件(一)土地に該当するとの上告人の主位的主張を認めることは困難であるとしても、上告人及びその先代が、上告人耕作地は一体として本件(一)土地であるとの認識の下に、長年にわたりこれを平穏に占有してきたことは原審の認定するところであって、上告人が前記予備的主張を維持していれば、上告人が時効により本件係争部分の所有権を取得したとして、本件所有権確認請求が認容されることも十分に考えられる(ちなみに、被上告人がD外一名から本件(二)土地を買い受けたのが右時効完成後であるとしても、原審の認定によれば、同土地が本件係争部分に含まれるか否かもまた確定し得ないことになるから、必ずしも上告人が本件係争部分の時効取得を被上告人に対抗し得ないことになるものではない。)。
そうすると、上告人がいったん取得時効の予備的主張を提出しながら、次回の口頭弁論期日に至ってこれを撤回したのは、上告人の誤解ないし不注意に基づくものとみられるのであって、原審としては、右撤回について上告人の真意を釈明し、その結果、上告人が右予備的主張を維持するというのであれば、その主張に係る取得時効の成否について更に審理を尽くした上、本件係争部分の所有権の帰属について判断すべきものである。
したがって、原審が、右のような措置に出ることなく上告人の本件所有権確認請求を棄却したのは、釈明権の行使を怠り、ひいては審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわなければならず、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。これと同旨をいう論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れない。そこで、本件については、右部分について更に審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻すこととする。
主要事実と間接事実
原告の請求をその主張した請求原因事実に基づかず、主張しない事実関係に基づいて認容し、または、被告の抗弁をその主張にかかる事実以外の事実に基づいて採用し原告の請求を排斥することは、所論弁論主義に違反するもので、許されないところであるが、被告が原告の主張する請求原因事実を否認し、または原告が被告の抗弁事実を否認している場合に、事実審裁判所が右請求原因または抗弁として主張された事実を証拠上肯認することができない事情として、右事実と両立せず、かつ、相手方に主張立証責任のない事実を認定し、もつて右請求原因たる主張または抗弁の立証なしとして排斥することは、その認定にかかる事実が当事者によつて主張されていない場合でも弁論主義に違反するものではない。けだし、右の場合に主張者たる当事者が不利益を受けるのはもつぱら自己の主張にかかる請求原因事実または抗弁事実の立証ができなかつたためであつて、別個の事実が認定されたことの直接の結果ではないからである。本件についてこれをみるに、上告人において、訴外Dの被上告人に対する弁済を主張するについては、訴外Dにおいて債務の履行に適合する給付をしたことのほか、右給付が本件手形金債権によつて担保された原判示の原因債権に対応する債務の履行としてなされたものであることの二つの点を立証する責務を負うものであるところ、原判決は、その措辞に正鵠を欠く点はあるが、要するに、Dが被上告人に支払つた原判示の金員は、Dにおいて別に被上告人に対して負担していた五〇万円の借入金債務の内入れ弁済として支払つたものであることを認定することにより、上告人の抗弁は、後者の点についての立証を欠くものとしてこれを排斥したものと認められる。してみれば、原判決にはなんら弁論主義違背のかどはないものというべきである。また、原判決は、Dの支払にかかる金員は別口の債務に全額充当されることを確定したのであるから、原審が所論法定充当の規定の適用を考慮する余地はなかつたものであり、この点においても原判決に所論の違法はない。なお、口頭弁論を再開しなかつた原審の措置を違法として非難する所論は、裁判所の裁量に属する行為について不服を述べるものにすぎず、また、Dが前記金員の支払に際し、これを本件手形金の支払に充当すべき旨指定をしたとして、原審の事実認定を非難する所論は、記録によるも右指定をなした事実が原審で主張された事実は認められないから、その前提を欠くことに帰する。したがつて、論旨は、いずれも採用することができない。
間接事実の自白
上告人の父Dの被上告人らに対する三〇万円の貸金債権を相続により取得したことを請求の原因とする上告人の本訴請求に対し、被上告人らが、Dは右債権を訴外Eに譲渡した旨抗弁し、右債権譲渡の経緯について、Dは、Eよりその所有にかかる本件建物を代金七〇万円で買い受けたが、右代金決済の方法としてDが被上告人らに対して有する本件債権をEに譲渡した旨主張し、上告人が、第一審において右売買の事実を認めながら、原審において右自白は真実に反しかつ錯誤に基づくものであるからこれを取り消すと主張し、被上告人らが、右自白の取消に異議を留めたことは記録上明らかである。
しかし、被上告人らの前記抗弁における主要事実は「債権の譲渡」であつて、前記自白にかかる「本件建物の売買」は、右主要事実認定の資料となりうべき、いわゆる間接事実にすぎない。かかる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもないと解するのが相当である。しかるに、原審は、前記自白の取消は許されないものと判断し、自白によつて、DがEより本件建物を代金七〇万円で買い受けたという事実を確定し、右事実を資料として前記主要事実を認定したのであつて、原判決には、証拠資料たりえないものを事実認定の用に供した違法があり、右違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。
自白の撤回
当事者の自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上その自白は錯誤に出たものと認めることができるから原審において被上告人の供述其他の資料により被上告人の自白を真実に合致しないものと認めた上之を錯誤に基くものと認定したことは違法とはいえない。論旨は独自の見解に基くものであるから採用し難い。
証言拒絶権
民訴法は,公正な民事裁判の実現を目的として,何人も,証人として証言をすべき義務を負い(同法190条),一定の事由がある場合に限って例外的に証言を拒絶することができる旨定めている(同法196条,197条)。そして,同法197条1項3号は,「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には,証人は,証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは,その事項が公開されると,当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される(最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照)。もっとも,ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても,そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく,そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして,保護に値する秘密であるかどうかは,秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである。
報道関係者の取材源は,一般に,それがみだりに開示されると,報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ,将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり,報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になると解されるので,取材源の秘密は職業の秘密に当たるというべきである。そして,当該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる。
そして,この比較衡量にあたっては,次のような点が考慮されなければならない。
すなわち,報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の知る権利に奉仕するものである。したがって,思想の表明の自由と並んで,事実報道の自由は,表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない。また,このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには,報道の自由とともに,報道のための取材の自由も,憲法21条の精神に照らし,十分尊重に値するものといわなければならない(最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁参照)。取材の自由の持つ上記のような意義に照らして考えれば,取材源の秘密は,取材の自由を確保するために必要なものとして,重要な社会的価値を有するというべきである。そうすると,当該報道が公共の利益に関するものであって,その取材の手段,方法が一般の刑罰法令に触れるとか,取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく,しかも,当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため,当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く,そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には,当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり,証人は,原則として,当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。
文書の成立の真正(二段の推定)
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、右印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるところ(最高裁昭和三九年(オ)第七一号同年五月一二日第三小法廷判決・民集一八巻四号五九七頁ほか参照)、右にいう当該名義人の印章とは、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないが、当該名義人の印章であることを要し、名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれないと解するのを相当とする。
これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実によれば、「本件各修正申告書の上告人名下の印影を顕出した印章は、上告人ら親子の家庭で用いられている通常のいわゆる三文判であり、上告人のものと限つたものでない」というのであるから、右印章を本件各申告書の名義人である上告人の印章ということはできないのであつて、その印影が上告人の意思に基づいて顕出されたものとたやすく推定することは許されないといわなければならない。
文書提出義務の範囲
1 【要旨第一】ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法二二〇条四号ハ【引用者注:現二二〇条四号ニ】所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である。
2 これを本件についてみるに、記録によれば、銀行の貸出稟議書とは、支店長等の決裁限度を超える規模、内容の融資案件について、本部の決裁を求めるために作成されるものであって、通常は、融資の相手方、融資金額、資金使途、担保・保証、返済方法といった融資の内容に加え、銀行にとっての収益の見込み、融資の相手方の信用状況、融資の相手方に対する評価、融資についての担当者の意見などが記載され、それを受けて審査を行った本部の担当者、次長、部長など所定の決裁権者が当該貸出しを認めるか否かについて表明した意見が記載される文書であること、本件文書は、貸出稟議書及びこれと一体を成す本部認可書であって、いずれも抗告人がJに対する融資を決定する意思を形成する過程で、右のような点を確認、検討、審査するために作成されたものであることが明らかである。
3 右に述べた文書作成の目的や記載内容等からすると、銀行の貸出稟議書は、銀行内部において、融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成される文書であって、法令によってその作成が義務付けられたものでもなく、融資の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も記載されることが予定されているものである。したがって、【要旨第二】貸出稟議書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がない限り、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきである。そして、本件文書は、前記のとおり、右のような貸出稟議書及びこれと一体を成す本部認可書であり、本件において特段の事情の存在はうかがわれないから、いずれも「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるというべきであり、本件文書につき、抗告人に対し民訴法二二〇条四号に基づく提出義務を認めることはできない。
証明度
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
証明責任の転換
以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきである。
争点効
所論の別件訴訟について上告人(別件訴訟の被上告人)勝訴の確定判決があつた事実は、当裁判所に顕著な事実である。しかし、右別件訴訟における上告人(別件訴訟の被上告人)の請求原因は、被上告人(別件訴訟の上告人)所有にかかる原判決末尾添付の別紙目録記載の建物(以下単に「本件建物」という。)およびその敷地(以下両者を指称するときは、単に「本件不動産」という。)について、被上告人と上告人との間に売買契約が締結され、その旨の所有権移転登記を経由したが、被上告人(別件訴訟の上告人)が約定の明渡期日に至つても、本件建物を明け渡さないので、上告人(別件訴訟の被上告人)は、右契約の履行として本件建物の明渡および約定の明渡期日の翌日以降の右契約不履行による損害賠償としての金銭支払を求める、というのであり、右別件訴訟の確定判決は、被上告人(別件訴訟の上告人)主張の右契約の詐欺による取消の抗弁を排斥して、上告人(別件訴訟の被上告人)の請求原因を全部認容したものである。されば、右確定判決は、その理由において、本件売買契約の詐欺による取消の抗弁を排斥し、右売買契約が有効であること、現在の法律関係に引き直していえば、本件不動産が上告人(別件訴訟の被上告人)の所有であることを確認していても、訴訟物である本件建物の明渡請求権および右契約不履行による損害賠償としての金銭支払請求権の有無について既判力を有するにすぎず、本件建物の所有権の存否について、既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効、以下同様とする。)を有するものではない。一方、本件訴訟における被上告人の請求原因は、右本件不動産の売買契約が詐欺によつて取り消されたことを理由として、本件不動産の所有権に基づいて、すでに経由された前叙の所有権移転登記の抹消登記手続を求めるというにあるから、かりに、本件訴訟において、被上告人の右請求原因が認容され、被上告人勝訴の判決が確定したとしても、訴訟物である右抹消登記請求権の有無について既判力を有するにすぎず、本件不動産の所有権の存否については、既判力およびこれに類似する効力を有するものではない。以上のように、別件訴訟の確定判決の既判力と本件訴訟において被上告人勝訴の判決が確定した場合に生ずる既判力とは牴触衝突するところがなく、両訴訟の確定判決は、ともに本件不動産の所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力を有するものではないから、論旨は採るをえない。なお、右説示のとおり、両訴訟の確定判決は、ともに本件不動産の所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力を有するものではないから、上告人は、別に被上告人を被告として、本件不動産の所有権確認訴訟を提起し、右所有権の存否について既判力を有する確定判決を求めることができることは、いうまでもない。
一部請求
一個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して口頭弁論終結時における債権の現存額を確定し(最高裁平成二年(オ)第一一四六号同六年一一月二二日第三小法廷判決・民集四八巻七号一三五五頁参照)、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く現存しないときは右請求を棄却するのであって、当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、当該債権が全く現存しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。したがって、右判決が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。
基準時後の形成権
借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法四条二頃所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。けだし、(1) 建物買買請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃借人がこれを行使することにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2) したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、その事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく(最高裁昭和五二年(オ)第二六八号同五二年六月二〇日第二小法廷判決・裁判集民事一二一号六三頁)、訴訟法上も、前訴確定判決の既判力によって同権利の主張が遮断されることはないと解すべきものである、(3) そうすると、賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に建物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買取請求権行使の効果は、民事執行法三五条二項所定の口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に該当するものというべきであるからである。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
後遺症
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合には、訴訟物は、右債権の一部の存否のみであつて全部の存否ではなく、従つて、右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である(当裁判所昭和三五年(オ)第三五九号、同三七年八月一〇日言渡第二小法廷判決、民集一六巻八号一七二〇頁参照)。ところで、記録によれば、所論の前訴(東京地方裁判所昭和三一年(ワ)第九五〇四号、東京高等裁判所同三三年(ネ)第二五五九号、第二六二三号)における被上告人の請求は、被上告人主張の本件不法行為により惹起された損害のうち、右前訴の最終口頭弁論期日たる同三五年五月二五日までに支出された治療費を損害として主張しその賠償を求めるものであるところ、本件訴訟における被上告人の請求は、前記の口頭弁論期日後にその主張のような経緯で再手術を受けることを余儀なくされるにいたつたと主張し、右治療に要した費用を損害としてその賠償を請求するものであることが明らかである。右の事実によれば、所論の前訴と本件訴訟とはそれぞれ訴訟物を異にするから、前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばないというべきであり、原判決に所論の違法は存しない。所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用することができない。
反射効
所論は、要するに、上告人に対する前記判決は連帯保証債務の履行を命ずるものであるところ、その主債務は、右判決確定後、主債務関係の当事者である被上告人と右相続人ら間の確定判決により不存在と確定されたから、上告人は、連帯保証債務の附従性に基づき請求異議の訴により自己に対する前記判決の執行力の排除を求めることができる筋合であると主張する。そこで案ずるに、一般に保証人が、債権者からの保証債務履行請求訴訟において、主債務者勝訴の確定判決を援用することにより保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても、保証人がすでに保証人敗訴の確定判決を受けているときは、保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定しても、同判決が保証人敗訴の確定判決の基礎となつた事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としてされている以上、保証人は右主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にする余地はないものと解すべきである。けだし、保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、右確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではないと解すべきであり、また、保証人は、保証人敗訴の確定判決の効力として、その判決の基礎となつた事実審口頭弁論終結の時までに提出できたにもかかわらず提出しなかつた事実に基づいてはもはや債権者の権利を争うことは許されないと解すべきところ、保証人敗訴判決の確定後において主債務者勝訴の確定判決があつても、その勝訴の理由が保証人敗訴判決の基礎となつた事実審口頭弁論の終結後に生じた事由に基づくものでない限り、この主債務者勝訴判決を援用して、保証人敗訴の確定判決に対する請求異議事由とするのを認めることは、実質的には前記保証人敗訴の確定判決の効力により保証人が主張することのできない事実に基づいて再び債権者の権利を争うことを容認するのとなんら異なるところがないといえるからである。
和解と錯誤
しかし、原判決の適法に確定したところによれば、本件和解は、本件請求金額六二万九七七七円五〇銭の支払義務あるか否かが争の目的であつて、当事者である原告(被控訴人、被上告人)、被告(控訴人、上告人)が原判示のごとく互に譲歩をして右争を止めるため仮差押にかかる本件ジヤムを市場で一般に通用している特選D印苺ジヤムであることを前提とし、これを一箱当り三千円(一罐平均六二円五〇銭相当)と見込んで控訴人から被控訴人に代物弁済として引渡すことを約したものであるところ、本件ジヤムは、原判示のごとき粗悪品であつたから、本件和解に関与した被控訴会社の訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があつたというのであるから、原判決には所論のごとき法令の解釈に誤りがあるとは認められない。
和解の解除
訴訟が訴訟上の和解によつて終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至つたとしても、そのことによつては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであつて、和解によつて一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従つて右と異なる見解に立つて、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。
請求の交換的変更
然るに第一審判決が訴訟物として判断の対象としたものは前説示のとおり貸金債権であり、原審の認容した求償債権ではない。この両個の債権はその権利関係の当事者と金額とが同一であるというだけでその発生原因を異にし全然別異の存在たることは多言を要しない。そして本件控訴はいうまでもなく第一審判決に対してなされたものであり、原審の認容した求償債権は控訴審ではじめて主張されたものであつて第一審判決には何等の係りもない。原審が本件訴の変更を許すべきものとし、また求償債権に基づく新訴請求を認容すべしとの見解に到達したからとて、それは実質上初審としてなす裁判に外ならないのであるから第一審判決の当否、従つて本件控訴の理由の有無を解決するものではない。それ故原審は本件控訴を理由なきものとなすべきいわれはなく、単に新請求たる求償債権の存在を確定し「控訴人は被控訴人に対し金七一三、六二六円を支払わなければならない」旨の判決をなすべかりしものなのである。それは一見第一審判決と同旨の主文を徒らに繰り返えすが如き感を与えるかも知れないけれど、実は、法律上重大な意義を有する。けだし控訴を棄却する旨の判決は、民訴三八四条一項の法文上明らかなように第一審判決を相当とし維持さるべきことを宣告するものであり、この判決が確定することによつて第一審判決も確定し、その裁判の内容に従いそれに相応する既判力、執行力、形成力等を生ずるのである。同条二項にいわゆる「判決カ其ノ理由ニ依レハ不当ナル場合ニ於テモ他ノ理由ニ依リテ正当ナルトキ」とは、第一審判決でなされた判断そのものの正当性が判決の理由とするところによつては維持せられないが、他の理由によつて肯定される場合をいうのである。例えば第一審判決が原告主張の貸金債権が弁済により消滅したものとして原告の請求を排斥したものであるとき、控訴審においては弁済の事実は認められないけれど、免除の事実が認められ、結局当該貸金債権の消滅を確定した第一審判決の判断が維持し得るような場合をいうのであつて、本件のように第一審判決と第二審判決とがその判断の対象を異にし偶々その主文の文言が同一に帰するというが如き場合をも包含するものでないことは同条一項の法意に照らし疑なきところである。それ故原審が求償債権に基づく請求(新訴)を認容すべき旨を判示しながら主文で控訴棄却の判示をしたのは、前掲法条の適用を誤り理由齟齬の違法を来たしたものであり、原判決はこの点において破棄を免れず論旨は結局理由がある。
なお貸金債権に基づく請求に関して附言する。原判決は既に説示したとおり主文で控訴を棄却する旨判示しているけれども、それは原審で新たに提起された求償債権に基づく新訴に対する裁判であつて貸金債権を認容した第一審判決の当否、換言すれば本件控訴の理由の有無については実質上何等の裁判もしてはいない。この事は原判文を一読して容易に了解し得るところである。それ故原判決に対する上告申立によつては、該請求は適法に当審に移審せられることはない。然らばこの請求についての訴訟関係如何というに、これを明確にすべき資料は記録上存在しない。従つて次に述べるが如く起り得べき各場合の事情に従い必ずしも単一ではない。すなわち被上告人は原審において前説示の如く訴の変更をしている。元来、請求の原因を変更するというのは、旧訴の繋属中原告が新たな権利関係を訴訟物とする新訴を追加的に併合提起することを指称するのであり、この場合原告はなお旧訴を維持し、新訴と併存的にその審判を求めることがあり、また旧訴の維持し難きことを自認し新訴のみの審判を求めんとすることがある。しかし、この後者の場合においても訴の変更そのものが許さるべきものであるというだけでは、これによつて当然に旧訴の訴訟繋属が消滅するものではない。けだし訴の変更の許否ということは旧訴の繋属中新訴を追加的に提起することが許されるか否かの問題であり、一旦繋属した旧訴の訴訟繋属が消滅するか否かの問題とは係りないところだからである。もし原告がその一方的意思に基づいて旧訴の訴訟繋属を消滅せしめんとするならば、法律の定めるところに従いその取下をなすか、或はその請求の拠棄をしなければならない。訴は原告の任意提起するところであるが、一旦提起した訴の繋属を消滅せしめんとするには、相手方の訴訟上受くべき利益も尊重さるべきであり、原告の意思のみに放任さるべきではない。それ故法律は原告の一方的意思に基づき訴訟繋属の消滅を来たすべき訴の取下、請求の拠棄等に関しては相手方の利益保護を考慮して、これが規定を設けている。すなわち「訴ノ取下ハ相手方カ本案ニ付準備書面ヲ提出シ、準備手続ユ於ナ申述ヲ為シ又ハ口頭弁論ヲ為シタル後ニ在リテハ相手方ノ同意ヲ得ルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス」とされ(民訴二三六条二項、なお同条三項以下、並びに二三七条二項等参照)、また請求の抛棄はこれを調書に記載することによりその記載が確定判決と同一の効力を有するものとされているのである(同二〇三条)。されば原告が訴提起の当初から併合されていた請求の一につき既になしたる弁論の結果これを維持し得ないことを自認しこれを撤回せんとするならば、その請求を拠棄するか、または相手方の同意を得て訴の取下をしなければならない。このことは原告が訴の変更をなし、一旦旧訴と新訴につき併存的にその審判を求めた後、旧訴の維持すべからざることを悟つてその訴訟繋属を終了せしめんと欲する場合においても、その趣を異にするものではない。果して然りとすれば原告が交替的に訴の変更をなし、旧訴に替え新訴のみの審理を求めんとする場合においてもその理を一にするものといわなければならない。何となればただ原告が訴の変更と同時に旧訴の訴訟繋属を消滅せしめんと欲したというだけで、相手方保護の必要を無視して直ちに旧訴の訴訟繋属消滅の効果を認むべきいわれはないからである。
主観的追加的併合
しかし、甲が、乙を被告として提起した訴訟(以下「旧訴訟」という。)の係属後に丙を被告とする請求を旧訴訟に追加して一個の判決を得ようとする場合は、甲は、丙に対する別訴(以下「新訴」という。)を提起したうえで、法一三二条【引用者注:現一五二条】の規定による口頭弁論の併合を裁判所に促し、併合につき裁判所の判断を受けるべきであり、仮に新旧両訴訟の目的たる権利又は義務につき法五九条【引用者注:現三八条】所定の共同訴訟の要件が具備する場合であっても、新訴が法一三二条の適用をまたずに当然に旧訴訟に併合されるとの効果を認めることはできないというべきである。けだし、かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでもなく、かえって訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによっては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。
固有必要的共同訴訟の成否
被上告人の被告Dに対する本訴請求が本件土地の所有権に基づいてその地上にある建物の所有者である同被告に対し建物収去土地明渡を求めるものであることは記録上明らかであるから、同被告が死亡した場合には、かりにEが同被告の相続人の一人であるとすれば、Eは当然に同被告の地位を承継し、右請求について当事者の地位を取得することは当然である。しかし、土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。けだし、右の場合、共同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求において理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務を負うのであつて、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を提起し、同時に判決を得ることを要しないからである。もし論旨のいうごとくこれを固有必要的共同訴訟であると解するならば、共同相続人の全部を共同の被告としなければ被告たる当事者適格を有しないことになるのであるが、そうだとすると、原告は、建物収去土地明渡の義務あることについて争う意思を全く有しない共同相続人をも被告としなければならないわけであり、また被告たる共同相続人のうちで訴訟進行中に原告の主張を認めるにいたつた者がある場合でも、当該被告がこれを認諾し、または原告がこれに対する訴を取り下げる等の手段に出ることができず、いたずらに無用の手続を重ねなければならないことになるのである。のみならず、相続登記のない家屋を数人の共同相続人が所有してその敷地を不法に占拠しているような場合には、その所有者が果して何びとであるかを明らかにしえないことが稀ではない。そのような場合は、その一部の者を手続に加えなかつたために、既になされた訴訟手続ないし判決が無効に帰するおそれもあるのである。以上のように、これを必要的共同訴訟と解するならば、手続上の不経済と不安定を招来するおそれなしとしないのであつて、これらの障碍を避けるためにも、これを必要的共同訴訟と解しないのが相当である。また、他面、これを通常の共同訴訟であると解したとしても、一般に、土地所有者は、共同相続人各自に対して債務名義を取得するか、あるいはその同意をえたうえでなければ、その強制執行をすることが許されないのであるから、かく解することが、直ちに、被告の権利保護に欠けるものとはいえないのである。そうであれば、本件において、所論の如く、他に同被告の承継人が存在する場合であつても、受継手続を了した者のみについて手続を進行し、その者との関係においてのみ審理判決することを妨げる理由はないから、原審の手続には、ひつきよう、所論の違法はないことに帰する。したがつて、論旨は採用できない。
補助参加の要件
しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)民訴法42条所定の補助参加が認められるのは,専ら訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られ,単に事実上の利害関係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない(最高裁昭和38年(オ)第722号同39年1月23日第一小法廷判決・裁判集民事71号271頁参照)。そして,法律上の利害関係を有する場合とは,当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される。
(2)【要旨】取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において,株式会社は,特段の事情がない限り,取締役を補助するため訴訟に参加することが許されると解するのが相当である。けだし,取締役の個人的な権限逸脱行為ではなく,取締役会の意思決定の違法を原因とする,株式会社の取締役に対する損害賠償請求が認められれば,その取締役会の意思決定を前提として形成された株式会社の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがあるというべきであり,株式会社は,取締役の敗訴を防ぐことに法律上の利害関係を有するということができるからである。そして,株式会社が株主代表訴訟につき中立的立場を採るか補助参加をするかはそれ自体が取締役の責任にかかわる経営判断の一つであることからすると,補助参加を認めたからといって,株主の利益を害するような補助参加がされ,公正妥当な訴訟運営が損なわれるとまではいえず,それによる著しい訴訟の遅延や複雑化を招くおそれはなく,また,会社側からの訴訟資料,証拠資料の提出が期待され,その結果として審理の充実が図られる利点も認められる。
補助参加の効力
まず、民訴法七〇条【引用者注:現四六条】の定める判決の補助参加人に対する効力の性質およびその効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、この効力は、いわゆる既判力ではなく、それとは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、その訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、これに協力しえたにもかかわらず、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至つたときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法七〇条が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、同法七八条【引用者注:現五三条】が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法七〇条は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが合理的であるからである。
独立当事者参加
思うに、債権者が民法四二三条一項の規定により代位権を行使して第三債務者に対し訴を提起した場合であつても、債務者が民訴法七一条により右代位訴訟に参加し第三債務者に対し右代位訴訟と訴訟物を同じくする訴を提起することは、民訴法二三一条【引用者注:現一四二条】の重複起訴禁止にふれるものではないと解するのが相当である。けだし、この場合は、同一訴訟物を目的とする訴訟の係属にかかわらず債務者の利益擁護のため訴を提起する特別の必要を認めることができるのであり、また、債務者の提起した訴と右代位訴訟とは併合審理が強制され、訴訟の目的は合一に確定されるのであるから、重複起訴禁止の理由である審判の重複による不経済、既判力抵触の可能性および被告の応訴の煩という弊害がないからである。したがつて、債務者の右訴は、債権者の代位訴訟が係属しているというだけでただちに不適法として排斥されるべきものと解すべきではない。もつとも、債権者が適法に代位権行使に着手した場合において、債務者に対しその事実を通知するかまたは債務者がこれを了知したときは、債務者は代位の目的となつた権利につき債権者の代位権行使を妨げるような処分をする権能を失い、したがつて、右処分行為と目される訴を提起することができなくなる(大審院昭和一三年(オ)第一九〇一号同一四年五月一六日判決・民集一八巻九号五五七頁参照)のであつて、この理は、債務者の訴提起が前記参加による場合であつても異なるものではない。したがつて、審理の結果債権者の代位権行使が適法であること、すなわち、債権者が代位の目的となつた権利につき訴訟追行権を有していることが判明したときは、債務者は右権利につき訴訟追行権を有せず、当事者適格を欠くものとして、その訴は不適法といわざるをえない反面、債権者が右訴訟追行権を有しないことが判明したときは、債務者はその訴訟追行権を失つていないものとして、その訴は適法ということができる。
承継人
賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法七四条【引用者注:現五〇条】にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル」者に該当すると解するのが相当である。けだし、土地賃借人が契約の終了に基づいて土地賃貸人に対して負担する地上建物の収去義務は、右建物から立ち退く義務を包含するものであり、当該建物収去義務の存否に関する紛争のうち建物からの退去にかかる部分は、第三者が土地賃借人から係争建物の一部および建物敷地の占有を承継することによつて、第三者の土地賃貸人に対する退去義務の存否に関する紛争という型態をとつて、右両者間に移行し、第三者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと解されるからである。これを実質的に考察しても、第三者の占有の適否ないし土地賃貸人に対する退去義務の存否は、帰するところ、土地賃貸借契約が終了していないとする土地賃借人の主張とこれを支える証拠関係(訴訟資料)に依存するとともに、他面において、土地賃貸人側の反対の訴訟資料によつて否定されうる関係にあるのが通常であるから、かかる場合、土地賃貸人が、第三者を相手どつて新たに訴訟を提起する代わりに、土地賃借人との間の既存の訴訟を第三者に承継させて、従前の訴訟資料を利用し、争いの実効的な解決を計ろうとする要請は、民訴法七四条の法意に鑑み、正当なものとしてこれを是認すべきであるし、これにより第三者の利益を損うものとは考えられないのである。そして、たとえ、土地賃貸人の第三者に対する請求が土地所有権に基づく物上請求であり、土地賃借人に対する請求が債権的請求であつて、前者と後者とが権利としての性質を異にするからといつて、叙上の理は左右されないというべきである。されば、本件土地賃貸借契約の終了を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中、土地賃借人であつた第一審被告亡Dからその所有の地上建物中の判示部分を賃借使用するにいたつた上告人Aに対して被上告人がした訴訟引受の申立を許容すべきものとした原審の判断は正当であり、所論は採用できない。
不利益変更禁止の原則
特定の金銭債権のうちの一部が訴訟上請求されているいわゆる一部請求の事件において、被告から相殺の抗弁が提出されてそれが理由がある場合には、まず、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、原告の請求に係る一部請求の額が残存額の範囲内であるときはそのまま認容し、残存額を超えるときはその残存額の限度でこれを認容すべきである。けだし、一部請求は、特定の金銭債権について、その数量的な一部を少なくともその範囲においては請求権が現存するとして請求するものであるので、右債権の総額が何らかの理由で減少している場合に、債権の総額からではなく、一部請求の額から減少額の全額又は債権総額に対する一部請求の額の割合で案分した額を控除して認容額を決することは、一部請求を認める趣旨に反するからである。
そして、一部請求において、確定判決の既判力は、当該債権の訴訟上請求されなかった残部の存否には及ばないとすること判例であり(最高裁昭和三五年(オ)第三五九号同三七年八月一〇日第二小法廷判決・民集一六巻八号一七二〇頁)、相殺の抗弁により自働債権の存否について既判力が生ずるのは、請求の範囲に対して「相殺ヲ以テ対抗シタル額」に限られるから、当該債権の総額から自働債権の額を控除した結果残存額が一部請求の額を超えるときは、一部請求の額を超える範囲の自働債権の存否については既判力を生じない。したがって、一部請求を認容した第一審判決に対し、被告のみが控訴し、控訴審において新たに主張された相殺の抗弁が理由がある場合に、控訴審において、まず当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を超えるとして控訴を棄却しても、不利益変更禁止の原則に反するものではない。
そうすると、原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告人の請求債権の総額を第一審の認定額を超えて確定し、その上で上告人が原審において新たに主張した相殺の自働債権の額を請求債権の総額から控除し、その残存額が第一審判決の認容額を超えるとして上告人の控訴を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。