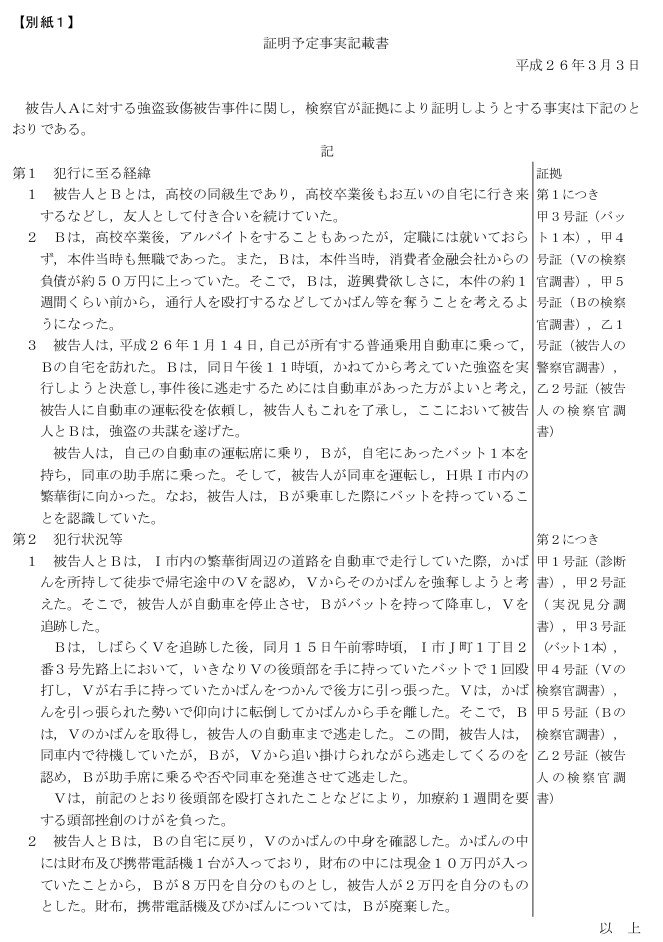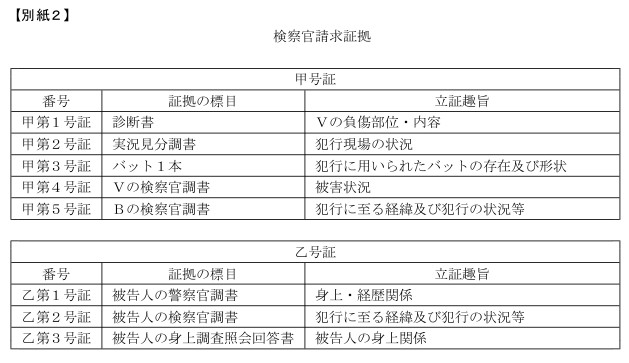問題
〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)
次の【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由していることを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結しており,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。
そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告として,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。
平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。
〔設問1〕
上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,Xは,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対する建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えているが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そして,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地の所有権を有することを争いたいと考えている。
ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたことを認める旨の陳述をした。
① Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合
② Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合
③ Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合
のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。
練習答案(実際の試験での再現答案)
(E評価)
以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
Wが自ら独立当事者参加(第47条)や義務承継人の訴訟引受け(第50条)を行えばXの目的が達成されるが、それではW次第ということになってしまうので、ここではXが主導的に行える方法を検討する。
1.義務承継人の訴訟引受け(第50条)
本件訴訟の目的物は、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことである。それをWがYから承継したので、当事者であるXの申立てにより、裁判所は、決定で、Wに訴訟を引き受けさせることができる(第50条第1項)。YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり、本件訴訟継続以前であるが、Xはそのことを知らなかったのであって、当事者であるYやWの同意があれば訴訟引受けを認めても問題ないだろう。
2.訴えの変更(第143条)
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の集結に至るまで、請求を変更することができる(第143条第1項)。本件では当事者がYからWに変更されるものの、Xの所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めるという点で請求の基礎に変更がないと言えるので、請求を変更することができると考えられる。訴訟が始まったばかりなので、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることもない。この場合、請求の変更は書面でしなければならず(第143条第2項)、相手方に送達しなければならない(第143条第3項)。
3.別訴の提起+弁論の併合(第152条)
訴えの変更に係る請求の基礎の変更を厳格に解してこれを認めないとするなら、Wを被告として別訴を提起して、それをYを被告とする訴訟に弁論の併合をすることもできる。こうすることでも、Wに対する建物退去土地明渡請求について、本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいというXの願望は満たされる。
[設問2]
① このYの陳述はWに影響しない
Wは本件訴訟に独立当事者参加(第47条)したと考えられる。Yがこの陳述をしたのがWの参加前なら、Wは当事者ではなく、どうすることもできなかったので、このYの陳述がWに影響することはない。
② このYの陳述はWに影響しない
①と同様に、Wは独立当事者参加をしたと考えられる。Wが本件訴訟に当事者として参加した後にYがこの陳述をしたという点で①と異なる。この場合、第47条第4項を経由して第40条第1項から第3項までの規定が準用される。そうすると、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる(第40条第1項)。このYの陳述はXの所有権を認めることにつながるので、Wにとって利益にはならない。よってこのYの陳述はWに影響しない。
③ このYの陳述はWに影響する
これは義務承継人の訴訟引受け(第50条)であると考えられる。その場合は、第41条第1項及び第3項が準用される(第50条第3項)。そうすると、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない(第41条第1項)ので、必然的にYの陳述がWに影響することになる。
以上
修正答案
以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
第1 義務承継人の訴訟引受け
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができるが(50条1項)、本問でWがYから建物退去土地明渡という訴訟の目的である義務を承継したのは、訴訟の係属前の平成26年2月10日であるので、この義務承継人の訴訟引受けはなし得ない。
第2 別訴の提起+弁論の併合
まず、Xは、Wを被告として、甲土地の所有権に基づき、乙建物を退去して甲土地を明け渡すことを求める別訴を提起することができる。
そして、裁判所は口頭弁論の併合を命じることができるので(152条1項)、Xとしてはその別訴とYを被告とした本訴の口頭弁論の併合を求めることになる。もっとも、弁論の併合には裁判所の裁量が認められるので、Xの望むように併合されるとは限らない。
第3 訴えの主観的追加的併合
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる(143条本文)。この条文からは、請求の変更として、新たに被告を追加することができるかどうかは定かではない。よって他の方法とも比較しながら、原告にとっての必要性、被告として追加される者の不利益、訴訟経済などを総合的に考慮して、これが認められるかどうかを検討する。
先にも述べたように、義務承継が訴訟継続中であれば、訴訟引受けが可能である。また、Xが、訴訟継続前に、Wに乙建物が賃貸されたことに気づいていれば、YとWを共同訴訟人として訴えることができた(38条1項)。乙建物を退去(収去)して甲土地を明け渡すという義務が共通しているからである。本問のような場合だけが制度の隙間になっている。
手続を一元化できることに加えて貼用印紙額の観点からも、原告Xにとっての必要性は高い。これが認められたとしても共同訴訟人独立の原則がはたらくので(39条)、被告に追加されるWにとって大きな不利益はない。そして本問では追加を認めても、YW間の乙建物の賃貸借について審判する必要が生じるくらいで、訴訟がそれほど複雑になることもない。Xは自らの目的を達するためにはいずれにしてもWを訴えることになるので、濫訴とも言えない。
以上より、Xは、本件訴訟において、訴えの主観的追加的併合により、Wへの請求もすることができる。
[設問2]
第1 前提(Yの陳述の意義)
相手方の主張する、自己に不利益な事実の承認は自白と呼ばれる。自白が成立するとその事実を証明することを要しなくなる(179条)。そして原則的に自白を撤回することはできない。
AX間で本件売買契約が締結されたことを認める旨のYの陳述は、相手方に証明義務のある事実の承認なので、不利益な事実の承認であり、自白である。よってYは原則的にこの自白を撤回することはできない。
第2 各場合の検討
①
Wは、訴訟の目的である、乙建物を退去して甲土地を明け渡すという義務を承継したと主張して第三者であるYの訴訟に参加している(51条)。これは訴訟上の地位も含めて承継する意思の表れであると解釈できるので、WはYと同様、原則的にこの自白を撤回することができない。つまり、AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして、Xが甲土地の所有権を有することを争うことはできない。
②
Wは、訴訟の目的である、乙建物を退去して甲土地を明け渡すという義務を承継したと主張して第三者であるYの訴訟に参加しているので、47条から49条の規定(独立当事者参加に関する規定)が準用される(51条)。その結果、40条1項から3項までの規定(必要的共同訴訟に関する規定)が準用され(47条4項)、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる(40条1項)。
Yのこの陳述は、Wが請求を受けている相手方Xに証明義務のある事実の承認であり、Wの利益にはならないので、その効力は生じない。つまり、AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして、Xが甲土地の所有権を有することを争うことができる。
③
Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をしたので、これは義務承継人の訴訟引受けである(50条1項)。よって、41条1項及び3項の規定(同時審判の申出がある共同訴訟に関する規定)が準用される(50条3項)。②とは異なり40条1項が準用されていないので、共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当する。
以上より、Yのこの陳述は、共同訴訟人であるWに影響しないので、AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして、Xが甲土地の所有権を有することを争うことができる。
以上
感想
[設問2]がややこしいです。問題にはありませんが、Yの陳述後に義務承継人の訴訟引受け(50条1項)があったらどうなるのだろうという疑問も残ります。やはり自らの意思で参加したのではない以上、AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして、Xが甲土地の所有権を有することを争うことができることになり、同時審判の範囲内でYの自白の効果が失われるのでしょうか。