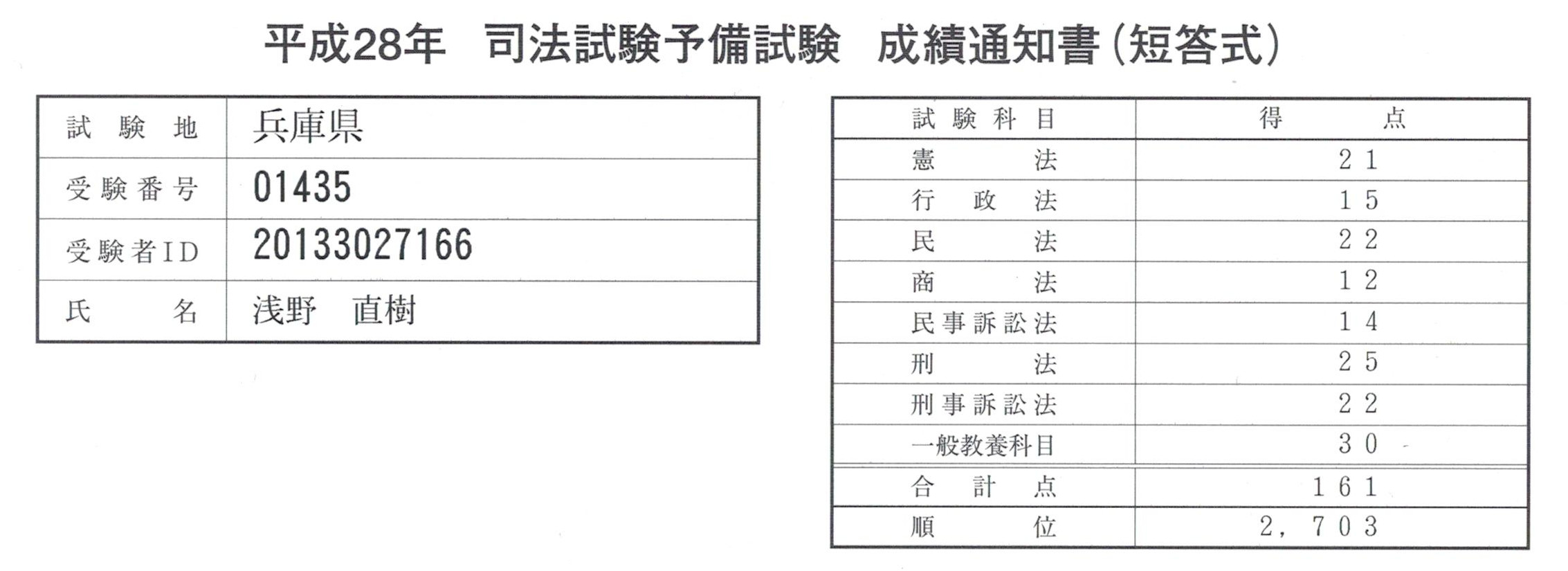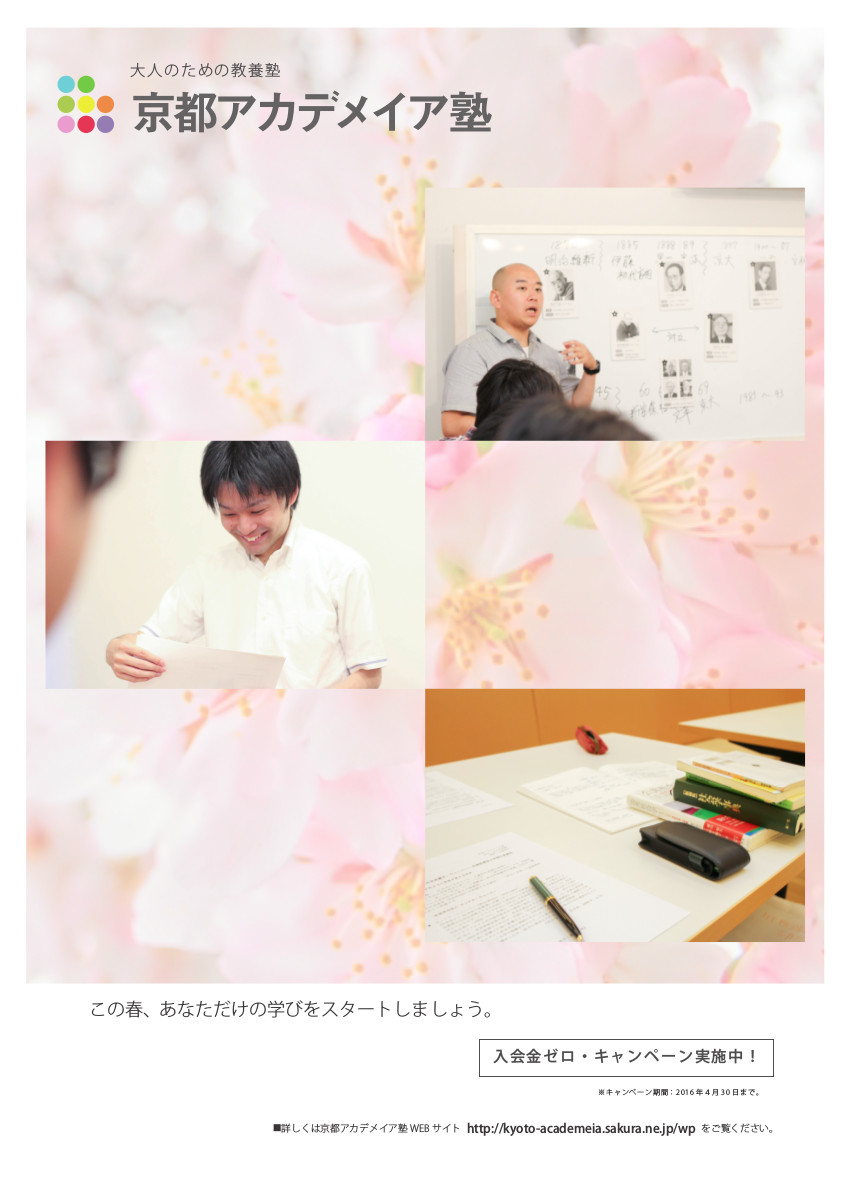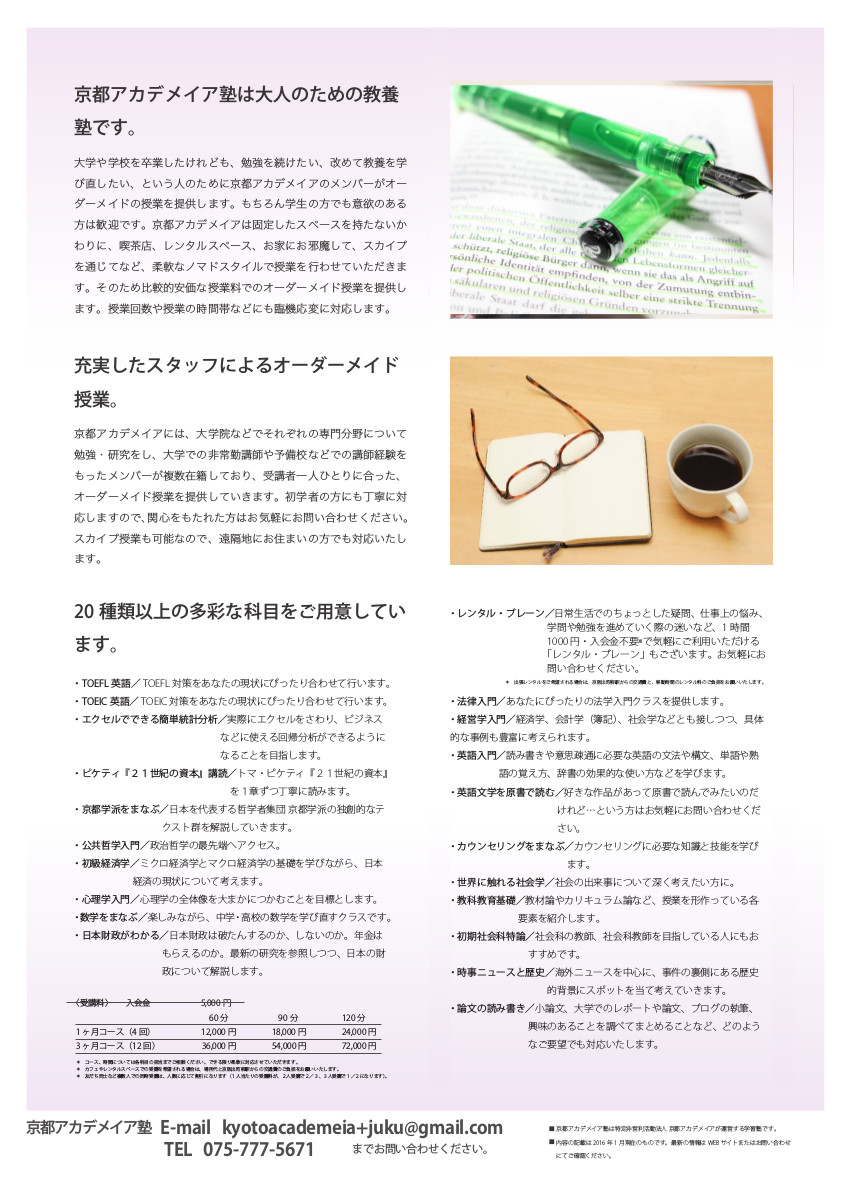複利計算(平均成長率)の計算についてまとめます。数学的な概念の理解から手計算でのやり方、excelなどの表計算ソフトあるいはgoogle検索でのやり方まで網羅します。対数(log)の定義と基本性質を理解していることを前提にしています。手計算をする際にたびたび用いる常用対数表はインターネット上で検索すればすぐに見つかりますし、数学の教科書などに付属していることも多いです。
1.元金と利率から所定年後の満期金額を求める(基準年度の値と成長率から所定年後の値を求める)
100万円を5%の利率で15年預けたら満期時にいくらになるかという例を考えてみましょう。利率が5%というのは2000年以降の日本では考えにくい数字ですが、他の時代や国では十分あり得る数字です。100万円の売上高が毎年5%ずつ成長したら15年後の売上高はいくらになるかというのも同じことですね。求める金額を$x$とすると次の式が成り立ちます。
$x=100\times(1.05)^{15}$
1年目で最初の100万円が1.05倍になり、2年目でそれがさらに1.05倍になり…15年目では(1.05)$^{15}$倍になると考えるのです。
(1)手計算
根気よく1.05を15回かければ求めることができますが、電卓を使ってもそれなりに大変です。こういう場合は対数を使うと計算が楽になります。
$x=100\times(1.05)^{15}$
両辺を100で割って
$\frac{x}{100}=(1.05)^{15}$
両辺の常用対数(底が10の対数)を取って
$\log_{10}{\frac{x}{100}}=\log_{10}{(1.05)^{15}}$
$\log_{10}{\frac{x}{100}}=15\log_{10}{(1.05)}$
常用対数表より
$\log_{10}{\frac{x}{100}}=15\times{0.0212}$
$\log_{10}{\frac{x}{100}}=0.318$
常用対数表を逆に読んで
$\frac{x}{100}=2.08$
$x=208$
と求めることができました。約208万円になるのですね。
(2)excelなどの表計算ソフト
「=100*(1.05)^(15)」と入力すれば一発で207.89…と求められます。
(3)google検索
同様に「100*(1.05)^(15)」と検索窓に入力すれば207.89…と表示されます。
2.元金と所定年後の満期金額から利率を求める(基準年度の値と所定年後の値から成長率を求める)
100万円をある定期預金に入れておいたら15年後に200万円になったとときの利率は何%だったのかを求めたいという例を考えてみましょう。15年前の売上高が100万円で現在の売上高が200万円であるときの年平均成長率を求めると言ったほうが自然な状況です。いずれにしても求める利率を$y$%とすると次の式が成り立ちます。
$100\times(1+\frac{y}{100})^{15}=200$
これは少々難しいです。
(1)手計算
$100\times(1+\frac{y}{100})^{15}=200$
両辺を100で割って
$(1+\frac{y}{100})^{15}=2$
$(1+\frac{y}{100})=y’$と置くと
$(y’)^{15}=2$
両辺の常用対数を取って
$\log_{10}{(y’)^{15}}=\log_{10}{2}$
$15\log_{10}{(y’)}=\log_{10}{2}$
常用対数表より
$15\log_{10}{(y’)}=0.3010$
$\log_{10}{(y’)}=0.0201$
常用対数表を逆に読んで
$y’=1.05$
$y’$をもとに戻して
$1+\frac{y}{100}=1.05$
$\frac{y}{100}=0.05$
$y=5$
と5%だと求めることができました。常用対数表を用いる際に多少の誤差は生じています。
(2)excelなどの表計算ソフト
手計算のときと同じように$(1+\frac{y}{100})=y’$と置いて
$(y’)^{15}=2$
と変形しましょう。次に両辺を$\frac{1}{15}$乗して
$((y’)^{15})^{\frac{1}{15}}=2^{\frac{1}{15}}$
$y’=2^{\frac{1}{15}}$
と変形します。$2^{\frac{1}{15}}$は「=2^(1/15)」と入力すれば1.047…と求められます。
ここから
$1+\frac{y}{100}=1.047$
$\frac{y}{100}=0.047$
$y=4.7$
と4.7%と先ほどより細かく求めることができました。
(3)google検索
上記のexcelなどの表計算ソフトと全く同じ方法で求めます。「2^(1/15)」と検索窓に打ち込めば1.047…と表示されます。
3.元金と利率と満期金額から所定年数を求める(基準年度の値と成長率と目標値から所定年数を求める)
100万円を利率5%で預けて200万円になるまでに何年かかるかという例です。100万円の売上高が毎年5%ずつ成長して200万円になるまで何年かかるかと言い換えることもできます。求める年数を$z$年とすると以下の式が成り立ちます。
$100\times(1.05)^{z}=200$
これも式変形が必要になりそうです。
(1)手計算
$100\times(1.05)^{z}=200$
両辺を100で割って
$(1.05)^{z}=2$
両辺の常用対数を取って
$\log_{10}{(1.05)^{z}}=\log_{10}{2}$
$z\log_{10}{(1.05)}=\log_{10}{2}$
常用対数表より
$z\times{0.0212}=0.3010$
$z=14.198\cdots$
以上より、整数で答えるとすれば15年かかるとわかります。
(2)excelなどの表計算ソフト
$100\times(1.05)^{z}=200$
両辺を100で割って
$(1.05)^{z}=2$
まで変形します。対数(log)の定義より
$z=\log_{1.05}{2}$
です。excelなどの表計算ソフトにはlog(真数, 底)という関数があるはずなので「=log(2, 1.05)」とセルに入力すれば14.206…と表示されます。
(3)google検索
google検索での電卓にはlog(真数, 底)という機能が存在していないようです。そこで先ほどの式からひと工夫します。
$z=\log_{1.05}{2}$
底の変換公式により底を10に揃えて
$z=\frac{\log_{10}{2}}{\log_{10}{1.05}}$
これを活用して「log(2)/log(1.05)」と検索窓に打ち込めば14.206…と表示されます。
底の変換公式により底を$e$に揃えて
$z=\frac{\log_{e}{2}}{\log_{e}{1.05}}$
と変形して「ln(2)/ln(1.05)」と打ち込んでも同じ結果です。googleの電卓にはlogという底が10の対数と、lnという底が$e$の対数の二種類あります。
これで複利計算(平均成長率)の計算を網羅できたことでしょう。元金(基準年度の値)を求める場合も論理的には考えられますが、実用性に乏しいので省略させていただきました。