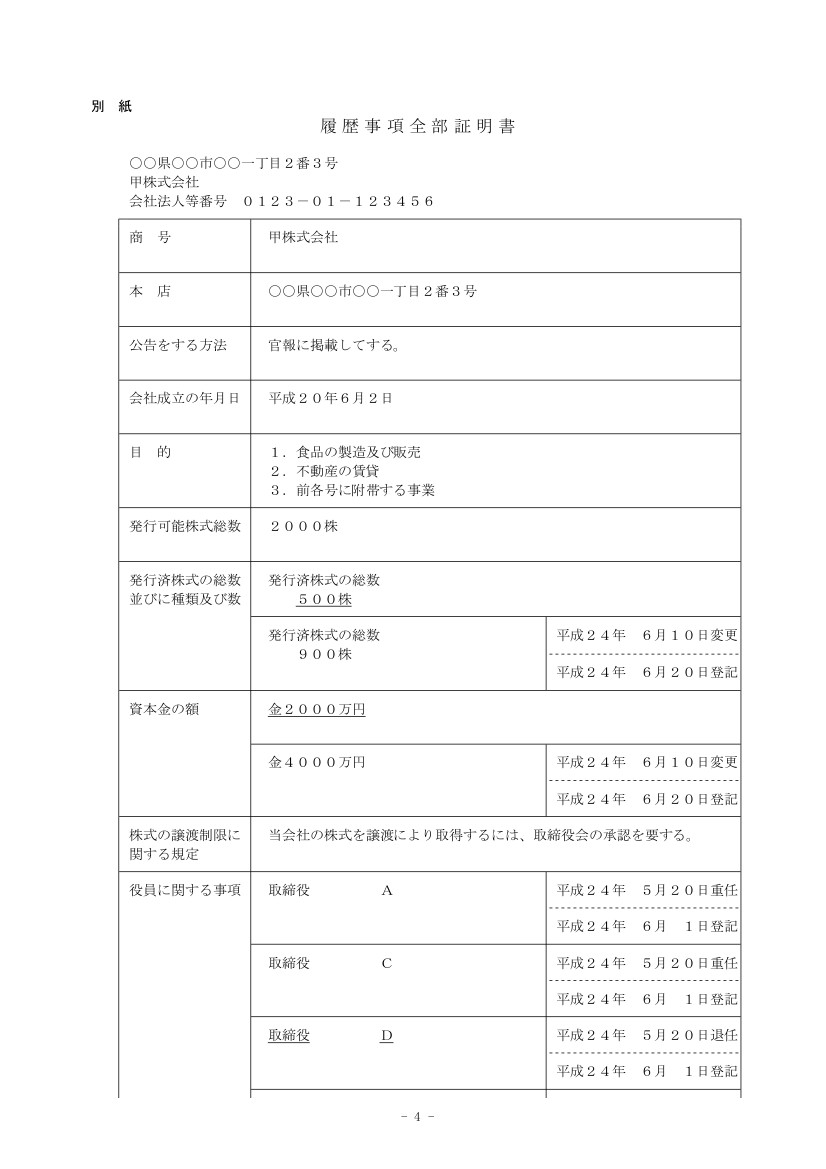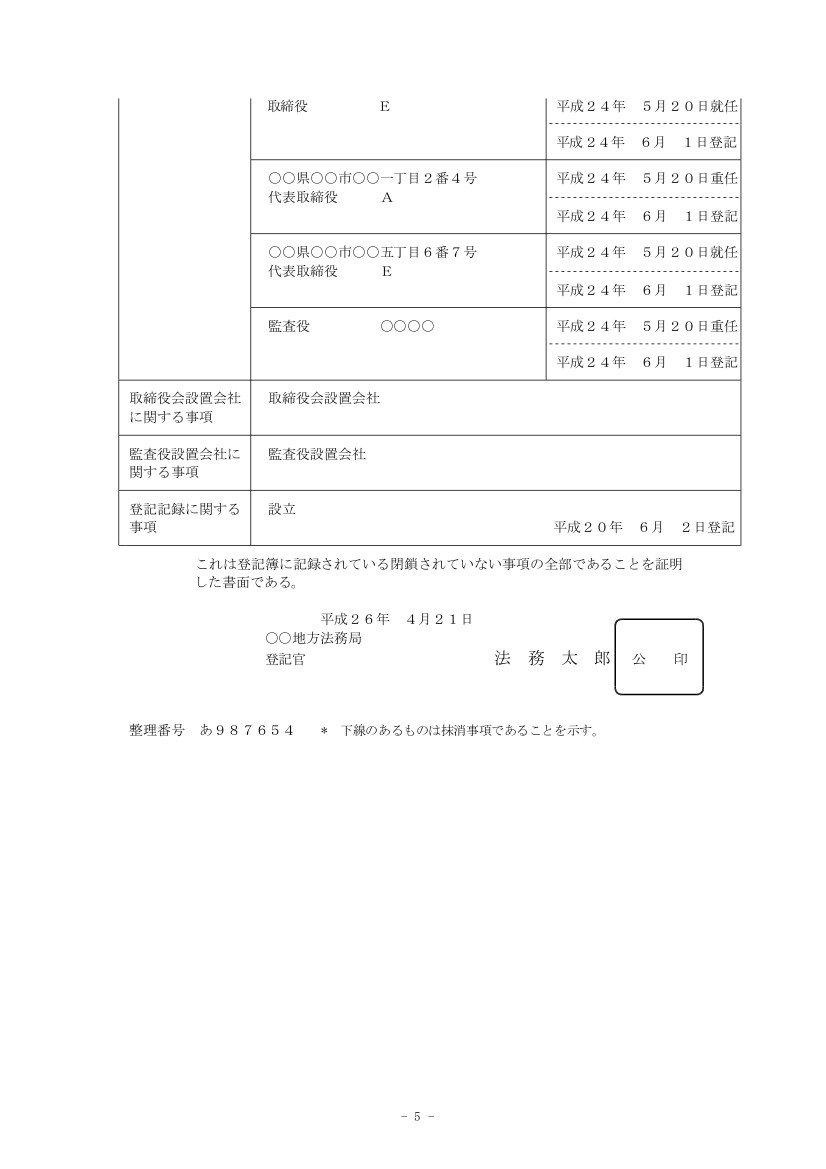問題
〔第1問〕(配点:100)
以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(23歳,女性)は,乙(24歳,男性)と婚姻し,某年3月1日(以下「某年」は省略する。),乙との間に長男Aを出産し,乙名義で借りたアパートの一室に暮らしていたが,Aを出産してから乙と不仲となった。乙は,甲と離婚しないまま別居することとなり,5月1日,同アパートから出て行った。乙は,その際,甲から,「二度とアパートには来ないで。アパートの鍵は置いていって。」と言われ,同アパートの玄関の鍵を甲に渡したものの,以前に作った合鍵1個を甲に内緒で引き続き所持していた。甲は,乙が出て行った後も名義を変えずに同アパート(以下「甲方」という。)にAと住み続け,自分でその家賃を支払うようになった。甲は,5月中旬頃,丙(30歳,男性)と知り合い,6月1日頃から,甲方において,丙と同棲するようになった。
2 丙は,甲と同棲を開始した後,家賃を除く甲やAとの生活に必要な費用を負担するとともに,育児に協力してAのおむつを交換したり,Aを入浴させるなどしていた。しかし,丙は,Aの連日の夜泣きにより寝不足となったことから,6月20日頃には,Aのことを疎ましく思うようになり,その頃からおむつ交換や入浴などの世話を一切しなくなった。
3 甲は,その後,丙がAのことを疎ましく思っていることに気付き,「このままAがいれば,丙との関係が保てなくなるのではないか。」と不安になり,思い悩んだ末,6月末頃,丙に気付かれないようにAを殺害することを決意した。Aは,容易に入手できる安価な市販の乳児用ミルクに対してはアレルギーがあり,母乳しか飲むことができなかったところ,甲は,「Aに授乳しなければ,数日で死亡するだろう。」と考え,7月1日朝の授乳を最後に,Aに授乳や水分補給(以下「授乳等」という。)を一切しなくなった。
このときまで,甲は,2時間ないし3時間おきにAに授乳し,Aは,順調に成育し,体重や栄養状態は標準的であり,特段の疾患や障害もなかった。通常,Aのような生後4か月の健康な乳児に授乳等を一切しなくなった場合,その時点から,①約24時間を超えると,脱水症状や体力消耗による生命の危険が生じ,②約48時間後までは,授乳等を再開すれば快復するものの,授乳等を再開しなければ生命の危険が次第に高まり,③約48時間を超えると,病院で適切な治療を受けさせない限り救命することが不可能となり,④約72時間を超えると,病院で適切な治療を受けさせても救命することが不可能となるとされている。
なお,甲は,Aを殺害しようとの意図を丙に察知されないように,Aに授乳等を一切しないほかは,Aのおむつ交換,着替え,入浴などは通常どおりに行った。
4 7月2日昼前には,Aに脱水症状や体力消耗による生命の危険が生じた。丙は,その頃,Aが頻繁に泣きながら手足をばたつかせるなどしているのに,甲が全くAに授乳等をしないことに気付き,甲の意図を察知した。しかし,丙は,「Aが死んでしまえば,夜泣きに悩まされずに済む。Aは自分の子でもないし,普通のミルクにはアレルギーがあるから,俺がミルクを与えるわけにもいかない。Aに授乳しないのは甲の責任だから,このままにしておこう。」と考え,このままではAが確実に死亡することになると思いながら,甲に対し,Aに授乳等をするように言うなどの措置は何ら講じず,見て見ぬふりをした。
甲は,丙が何も言わないことから,「丙は,私の意図に気付いていないに違いない。Aが死んでも,何らかの病気で死んだと思うだろう。丙が気付いて何か言ってきたら,Aを殺すことは諦めるしかないが,丙が何か言ってくるまではこのままにしていよう。」と考え,引き続き,Aに授乳等をしなかった。
5 7月3日昼には,Aの脱水症状や体力消耗は深刻なものとなり,病院で適切な治療を受けさせない限り救命することが不可能な状態となった。同日昼過ぎ,丙は,甲が買物に出掛けている間に,Aを溺愛している甲の母親から電話を受け,同日夕方にAの顔を見たいので甲方を訪問したいと言われた。Aは,同日夕方に病院に連れて行って適切な治療を受けさせれば,いまだ救命可能な状態にあったが,丙は,「甲の母親は,Aの衰弱した姿を見れば,必ず病院に連れて行く。そうなれば,Aが助かってしまう。」と考え,甲の母親に対し,甲らと出掛ける予定がないのに,「あいにく,今日は,これからみんなで出掛け,帰りも遅くなるので,またの機会にしてください。」などと嘘をつき,甲の母親は,やむなく,その日の甲方訪問を断念した。
6 7月3日夕方,甲は,目に見えて衰弱してきたAを見てかわいそうになり,Aを殺害するのをやめようと考え,Aへの授乳を再開し,以後,その翌日の昼前までの間,2時間ないし3時間おきにAに授乳した。しかし,Aは,いずれの授乳においても,衰弱のため,僅かしか母乳を飲まなかった。甲は,Aが早く快復するためには病院に連れて行くことが必要であると考えたが,病院から警察に通報されることを恐れ,「授乳を続ければ,少しずつ元気になるだろう。」と考えてAを病院に連れて行かなかった。
7 他方,乙は,知人から,甲が丙と同棲するようになったと聞き,「俺にも親権があるのだから,Aを自分の手で育てたい。」との思いを募らせていた。乙は,7月4日昼,歩いて甲方アパートの近くまで行き,甲方の様子をうかがっていたところ,甲と丙が外出して近所の食堂に入ったのを見た。乙は,甲らが外出している隙に,甲に無断でAを連れ去ろうと考え,持っていた合鍵を使い,玄関のドアを開けて甲方に立ち入り,Aを抱きかかえて甲方から連れ去った。
8 乙は,甲方から約300メートル離れた地点で,タクシーを拾おうと道路端の歩道上に立ち止まり,そこでAの顔を見たところ,Aがひどく衰弱していることに気付いた。乙は,「あいつら何をやっていたんだ。Aを連れ出して良かった。一刻も早くAを病院に連れて行こう。」と考え,走行してきたタクシーに向かって歩道上から手を挙げたところ,同タクシーの運転手が脇見をして乙に気付くのが遅れ,直前で無理に停車しようとしてハンドル及びブレーキ操作を誤った。そのため,同タクシーは,歩道に乗り上げ,Aを抱いていた乙に衝突して乙とAを路上に転倒させた。
9 乙とAは直ちに救急車で病院に搬送され,乙は治療を受けて一命をとりとめたものの,Aは病院到着時には既に死亡していた。司法解剖の結果,Aの死因は,タクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷であるが,他方で,Aの衰弱は深刻なものであり,仮に乙が事故に遭うことなくタクシーでAを病院に連れて行き,Aに適切な治療を受けさせたとしても,Aが助かる可能性はなく,1日ないし2日後には,衰弱により確実に死亡していたであろうことが判明した。
練習答案
以下刑法についてはその条数のみを示す。
第1 乙の罪責
(1) 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」(130条)。乙は結果的に衰弱したAを助け出そうとしたが、7月4日の昼に持っていた合鍵を使い、玄関のドアを開けて甲方に立ち入った際には「Aを自分の手で育てたい」というだけで甲に無断でAを連れ去ろうとしており、正当な理由がないと評価できる。甲方は、甲、丙、Aが生活する人の住居である。住居侵入罪の保護法益は、人の住居は一般にプライバシーの度合いが高く、そこに住む人はその住居に入れる人を選ぶことができるべきであるので、そこに住む人の管理権であると考える。甲は、乙に対し、「二度とアパートには来ないで。アパートの鍵は置いていって」と言っており、その管理権として乙を入れたくないという強い意思を有していた。この保護法益からすると、甲方の名義が乙のままであったことは罪の成立に消長をきたさない。以上より、乙は甲方に侵入したと言える。よって乙には甲方への住居侵入罪が成立する。
(2)未成年者略取罪
「未成年者を略取し…た者は、三月以上七年以下の懲役に処する」(224条)。Aは未成年者である。未成年者略取罪の保護法益は、未成年者の生命や身体などの権利であるが、その権利は一般に保護者を通じて守られるものである。親権者は、未成年者の子どもと別居していても保護者である。乙はAの親権者である。よって乙はAを略取したとは言えない。以上より乙に未成年者略取罪は成立しない。
(3)結論
乙には住居侵入罪のみが成立する。
第2 甲の罪責
(1)殺人罪
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(199条)。甲は、Aに授乳しないことにより、Aという人を殺したと言える。殺人罪は典型的には作為による殺人を想定しているが、不作為による殺人を排除するものではない。このような不真性不作為犯が成立するためには、一定の作為義務が存在し、その義務に違反したことが必要だと考える。そうしないと処罰範囲が広くなりすぎてしまう。甲はAの母親であり、Aの養育を自宅で引き受けていた。母親には子どもを扶養する義務があり、このような事情の下では、甲に、Aを授乳するなどして適切に養育する義務がある。そして甲はその義務に違反している。また、甲のAに授乳しないという不作為とA死亡との間に因果関係があるかも問題となり得る。Aの直接の死因は、タクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷だったからである。因果関係は、条件関係を前提として、社会的に相当な因果関係があるかどうかで判断する。甲の不作為がなければ(適切に授乳していれば)乙がAを病院に連れて行こうとすることもなく、タクシーに衝突されることもなかった。よって条件関係はある。Aの死因は脳挫傷だが、事故に遭うことなくタクシーでAを病院に連れて行き、Aに適切な治療を受けさせたとしても、Aが助かる可能性はなく、1日ないし2日後には、衰弱により確実に死亡していたであろうことが判明しているので、タクシーの衝突はAの死期を若干早めただけであり、甲の不作為とA死亡との間には、社会的に相当な因果関係がある。タクシーで病院に連れて行こうとすることと甲の不作為とが密接につながっているという事情もある。
甲はAを殺害することを決意して授乳を止めたので、故意に欠けるところもない。殺人の故意があるので、保護責任者遺棄致死罪(219条)ではない。違法性を阻却する事情もない。
以上より、甲には殺人罪が成立する。
*1
(2)結論
甲にはその他の罪責は見当たらないので、殺人罪が成立する。
第3 丙の罪責
(1)殺人罪の幇助
Aを殺害することに関して、甲と丙との間に意思連絡はなかった。明示的な意思連絡がなくても、特殊な関係下で黙示的な意思連絡があると認められる場合もあるが、本件ではお互いの意思をあやふやなまま推測しているにとどまり、黙示の意思連絡があったとも言えない。共同正犯(60条)には意思連絡が必要なので、本件では共同正犯は成立しない。
他方、「正犯を幇助した者は、従犯とする」(62条)の幇助には、意思連絡のない片面的幇助も含まれるというのが判例の立場である。そこで以下では幇助を検討する。
幇助と言うためには、正犯の罪の成立を、心理的物理的に助けたことが必要である。片面的幇助では心理的な助力は考えられないので、物理的な助力がなければならない。
丙は、甲が外出していた7月3日の昼過ぎに、甲の母親から電話を受け、このまま甲の母親が甲方に来ると衰弱したAを見て病院に連れていくだろうと考えて、これから外出するとうそをついて甲の母親の訪問を妨げた。これは甲によるA殺害を助けたと言える。よって丙には殺人罪の幇助が成立する。
先に述べたように、甲には保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人罪が成立するのであり、丙にその幇助が成立するのだから、別途丙に保護責任者遺棄致死罪が成立することはない。また、不作為の幇助を認めない理由もない。
(2)結論
以上より、丙には殺人罪の幇助が成立する。
*1
甲に中止犯が成立するかどうかを検討する。「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」(43条但書)。自己の意思によるとは、障害がないのに自分の任意で犯罪を中止することである。7月3日夕方、甲は衰弱したAを見てかわいそうになり、Aを殺害するのをやめようとして、Aへの授乳を再開した。授乳を再開せざるを得ないような外的な障害がなかったにもかかわらずそうしているので、自己の意思によると言える。犯罪を中止するというのは、犯罪の結果が発生する危険が生じる前であれば単に犯罪行為を中止するだけでよいが、その危険が生じた後は結果発生を防ぐべく手を尽くさなければならない。7月3日夕方時点では、Aに死の危険が生じている。よって単なる犯罪行為の中止(授乳の再開)だけでは足りず、結果発生を防ぐべく手を尽くす(救急車を呼ぶ等)ことが必要である。よって甲は犯罪を中止したとは言えないので、中止犯は成立しない。
以上
修正答案
以下刑法についてはその条数のみを示す。
第1 乙の罪責
(1) 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」(130条)。乙は結果的に衰弱したAを助け出そうとしたが、7月4日の昼に持っていた合鍵を使い、玄関のドアを開けて甲方に立ち入った際には「Aを自分の手で育てたい」というだけで甲に無断でAを連れ去ろうとしており、正当な理由がないと評価できる。甲方は、甲、丙、Aが生活する人の住居である。住居侵入罪の保護法益は、人の住居は一般にプライバシーの度合いが高く、そこに住む人はその住居に入れる人を選ぶことができるべきであるので、そこに住む人の管理権であると考える。甲は、乙に対し、「二度とアパートには来ないで。アパートの鍵は置いていって」と言っており、その管理権として乙を入れたくないという強い意思を有していた。この保護法益からすると、甲方の名義が乙のままであったことは罪の成立に消長をきたさない。以上より、乙は甲方に侵入したと言える。よって乙には甲方への住居侵入罪が成立する。
(2)未成年者略取罪
「未成年者を略取し…た者は、三月以上七年以下の懲役に処する」(224条)。Aは未成年者である。略取とは暴力や脅迫により被略取者を生活環境から引き離し、自己の支配下に置くことである。乙は合鍵を用いて甲方に侵入し、Aを抱きかかえて連れ去り、自己の手元に留めたので、略取したと言える。もっとも、乙はAの親権者であり、社会的に相当な行為として例外的に違法性が阻却されないかが問題となり得る。未成年者略取罪の保護法益は、未成年者の生命や身体などの権利である。結果的には衰弱したAを乙が病院へ連れて行こうとしたが、Aを連れ去った実行の着手の時点では、Aのために特段の必要性がないのに粗暴なやり方で判断能力のないAを連れ去っているので、社会的に相当だとして違法性が阻却されることはない。以上より乙に未成年者略取罪が成立する。
(3)結論
乙には住居侵入罪と未成年者略取罪が成立し、これらは牽連犯になる。
第2 甲の罪責
(1)殺人罪
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(199条)。甲は、Aに授乳しないことにより、Aという人を殺したと言えるかどうかを検討する。
(A)不真性不作為犯
殺人罪は典型的には作為による殺人を想定しているが、不作為による殺人を排除するものではない。このような不真性不作為犯が成立するためには、法律や先行行為などにより一定の作為義務が存在し、その作為が可能であるにもかかわらずその義務に違反したことが必要だと考える。そうしないと処罰範囲が広くなりすぎてしまう。甲はAの母親であり、Aの養育を自宅で引き受けていた。母親には法律上子どもを扶養する義務があり、このような事情の下では、甲に、Aを授乳するなどして適切に養育する義務がある。そして甲は授乳をすることができたのにその義務に違反している。7月2日昼前にはAに生命の危険が生じているので、この時点で甲には不作為によりAを殺すという実行の着手があったと言える。
(B)因果関係
また、甲のAに授乳しないという不作為とA死亡との間に因果関係があるかも問題となり得る。因果関係は、条件関係を前提として、社会経験上相当な因果関係があるかどうかで判断する。甲の不作為がなければ(適切に授乳していれば)乙が急いでAを病院に連れて行こうとすることもなく、タクシーに衝突されることもなかった。よって条件関係はある。しかし、授乳をしないことで衰弱させて乳児(A)を殺そうとした際に、何者か(乙)が合鍵を使って自宅に侵入してその乳児を連れ出し病院に向かう途中でタクシーに衝突されて脳挫傷で乳児が死亡するということは、一般人も甲も予見できず、社会経験上相当な因果関係はない。よって、既遂とはならず未遂である。
(C)中止犯
甲に中止犯が成立するかどうかを検討する。「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」(43条但書)。自己の意思によるとは、障害がないのに自分の任意で犯罪を中止することである。7月3日夕方、甲は衰弱したAを見てかわいそうになり、Aを殺害するのをやめようとして、Aへの授乳を再開した。授乳を再開せざるを得ないような外的な障害がなかったにもかかわらずそうしているので、自己の意思によると言える。犯罪を中止するというのは、犯罪の結果が発生する危険が生じる前であれば単に犯罪行為を中止するだけでよいが、その危険が生じた後は結果発生を防ぐべく手を尽くさなければならない。7月3日夕方時点では、Aに死の危険が生じている。よって単なる犯罪行為の中止(授乳の再開)だけでは足りず、結果発生を防ぐべく手を尽くす(救急車を呼ぶ等)ことが必要である。よって甲は犯罪を中止したとは言えないので、中止犯は成立しない。
(D)殺人罪の成否の結論
甲はAを殺害することを決意して授乳を止めたので、故意に欠けるところもない。殺人の故意があるので、保護責任者遺棄致死罪(219条)ではない。違法性を阻却する事情もない。
以上より、甲には殺人罪の未遂(203条)が成立する。
(2)結論
甲にはその他の罪責は見当たらないので、殺人罪が成立する。
第3 丙の罪責
(1)殺人罪
(A)単独正犯
甲と同様に、不作為による殺人罪の成否を検討する。丙はAの父親ではなく、A及び甲と同居してAのおむつ交換や入浴などの世話をしていたが、それはわずか20日ほどのことであり、Aの世話は甲が主として行っていたので、法律や先行行為などの事情から丙にAを養育するといった義務は生じていなかったと考えられる。よって丙に殺人罪の単独正犯が成立することはない。
(B)共同正犯
「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」(60条)。「共同して」というからには意思連絡が必要である。Aを殺害することに関して、甲と丙との間に意思連絡はなかった。明示的な意思連絡がなくても、特殊な関係下で黙示的な意思連絡があると認められる場合もあるが、本件ではお互いの意思をあやふやなまま推測しているにとどまり、黙示の意思連絡があったとも言えない。以上より、丙に殺人罪の共同正犯が成立することもない。
(C)幇助
「正犯を幇助した者は、従犯とする」(62条)の幇助には、意思連絡のない片面的幇助も含まれるというのが判例の立場である。そこで以下では幇助を検討する。
幇助と言うためには、正犯の罪の成立を容易にする行為を、それと認識,認容しつつ行い、実際に正犯行為が行われることによって成立する。片面的幇助では心理的な助力は考えられないので、物理的な助力がなければならない。
丙は、7月2日昼前に、甲が全くAに授乳等をしないことに気付き、このままではAが確実に死亡することになると思いながら、甲に対し、Aに授乳等をするように言うなどの措置は何ら講じなかった。同居する乳児の生命に危機が発生していることに気づいたら、他の人に助けを求めるなどしてその乳児の生命を救おうとする義務があると言える。丙はAやその他の人に助けを求めるなどすることができたのにそうせず前述の義務に違反し、それにより甲によるA殺害を容易にして、そのことを認識していたので、不作為により甲のA殺人を幇助したと言える。また、丙は、甲が外出していた7月3日の昼過ぎに、甲の母親から電話を受け、このまま甲の母親が甲方に来ると衰弱したAを見て病院に連れていくだろうと考えて、これから外出するとうそをついて甲の母親の訪問を妨げた。これは甲によるA殺害を容易にしたと言え、丙にはその認識もあった。よって丙には殺人罪の幇助が成立する。
(2)結論
以上より、丙には殺人罪の幇助が成立する。
以上